「1985年のクラッシュ・ギャルズ」(文藝春秋)柳澤 健 ― 2012年04月01日 17時17分26秒

これも面白くて一気に読んでしまいました。
なぜ面白いかと言うと、それは著者の柳澤健さんの筆が巧みだからです。
文章もうまいし、物語るのも大変うまいと思います。
要するに大変、文才に優れているということでしょう。
本書のタイトルは「1985年の〜〜」となっていますが、これはもちろん、前著の「1976年のアントニオ猪木」にならったものです。
こうしたタイトルを付けた以上は、どうしても「1976年の〜〜」と比較されてしまうと思いますが、それではちょっと可哀想な気がします。
この本は「1985年」うんぬんに関係なく、純粋に「評伝・クラッシュギャルズ」として読めばいいのでしょう。
この本には、狂言回しとして、あるプロレスファンの女性(最初は少女)が登場しますが、最初のうちは、その人が架空の人物なのか実在の人物なのかが分からず、読んでいてかなり不安になります。
読み進めれば、あ、おそらく実在の人だろうと想像がつきます。
柳澤さんは「あとがき」で、本名を明かしますが、これは冒頭で説明しておけば、もっと本の完成度が高まったような気がします。
つまり、彼女は架空の狂言回しではないと分かり、主人公の一人として読者は彼女の人生を追うことができたからです。
さて、この本を一般の人はどう読むのでしょうか?
ぼくは「女子プロレス」というものは、観たことがありませんが、「プロレス」という単純に一言では定義できない特殊なジャンルに幼い頃からずっと興味を持って接してきました。
「1976年のアントニオ猪木」は明らかに、プロレスをまったく知らない人でも、ものすごく興味を持って読むことができたと思います。
本書が、「プロレス」という枠を飛び越えたかどうかは、読者によって判断が分かれるかもしれません。
ですが、ぼくにとってはとても良質なノンフィクションとして記憶に残る一作になりました。
これからも柳澤さんの本を大いに注目して読んでいきたいです。
なぜ面白いかと言うと、それは著者の柳澤健さんの筆が巧みだからです。
文章もうまいし、物語るのも大変うまいと思います。
要するに大変、文才に優れているということでしょう。
本書のタイトルは「1985年の〜〜」となっていますが、これはもちろん、前著の「1976年のアントニオ猪木」にならったものです。
こうしたタイトルを付けた以上は、どうしても「1976年の〜〜」と比較されてしまうと思いますが、それではちょっと可哀想な気がします。
この本は「1985年」うんぬんに関係なく、純粋に「評伝・クラッシュギャルズ」として読めばいいのでしょう。
この本には、狂言回しとして、あるプロレスファンの女性(最初は少女)が登場しますが、最初のうちは、その人が架空の人物なのか実在の人物なのかが分からず、読んでいてかなり不安になります。
読み進めれば、あ、おそらく実在の人だろうと想像がつきます。
柳澤さんは「あとがき」で、本名を明かしますが、これは冒頭で説明しておけば、もっと本の完成度が高まったような気がします。
つまり、彼女は架空の狂言回しではないと分かり、主人公の一人として読者は彼女の人生を追うことができたからです。
さて、この本を一般の人はどう読むのでしょうか?
ぼくは「女子プロレス」というものは、観たことがありませんが、「プロレス」という単純に一言では定義できない特殊なジャンルに幼い頃からずっと興味を持って接してきました。
「1976年のアントニオ猪木」は明らかに、プロレスをまったく知らない人でも、ものすごく興味を持って読むことができたと思います。
本書が、「プロレス」という枠を飛び越えたかどうかは、読者によって判断が分かれるかもしれません。
ですが、ぼくにとってはとても良質なノンフィクションとして記憶に残る一作になりました。
これからも柳澤さんの本を大いに注目して読んでいきたいです。
最終回です! ― 2012年04月02日 19時41分56秒
講談社の「g2」に連載されている「ドキュメント小児外科病棟 30時間」が、今日更新されました。
今週で最終回になります。
時間のある方はぜひ目を通してください。
そしてこれまで読んでくださった方はには、厚く御礼申し上げます。
http://g2.kodansha.co.jp/
また、「g2」でお会いできるといいですね。
今週で最終回になります。
時間のある方はぜひ目を通してください。
そしてこれまで読んでくださった方はには、厚く御礼申し上げます。
http://g2.kodansha.co.jp/
また、「g2」でお会いできるといいですね。
「メルトダウン ドキュメント福島第一原発事故」 (講談社)大鹿 靖明 ― 2012年04月03日 22時44分56秒
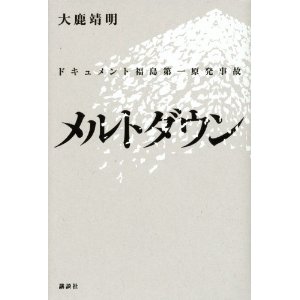
読んでいて気持ちが完全に萎えてしまいました。
ある意味、こんなに不愉快な本はありません。
いえ、それは大鹿さんが悪いといういう意味では全然なくて、東電のあまりにも無責任な態度が不愉快なのです。
地球最大規模の福島原発事故が起きた時、東電はどうやって事故を制御すればいいか全然分かっていませんでした。
それはそうでしょう。
「事故は起きない」という「決まり」になっていたのだから、「対処法」などは存在しません。
一般の人々が、肝臓がんの手術をやれと言われても、まったく何もできないのと同じです。
東電の社長も会長も、何をどうしたらいいか意志決定ができず、ただ呆然としていたのです。
彼らが考えたのは、これ以上は危険だから原発から撤退するという決断だけでした。
泣けてくるじゃないですか。
そしてこれだけの大惨事が起きても、原発推進を貫き通そうとする経産省。
すごいですね、官僚って。
自分たちが生き残ることが自己目的になって、役所が存在するんですね。
天下りの構造なんて絶対に断ち切ることはできませんよ。
「みんなの党」が政権を取ってもそれは不可能でしょう。
政治家は、官僚がいなければ何もできないし、官僚は決して時の政権政党の味方とは限りませんからね。
しかし、恐るべきは自民党です。
経産省・東電・財界・学会と一体となって日本中に原発を作ってきて、その挙げ句、自爆したのにもかかわらず、一切責任を取らないで、これを利用して民主党政権を倒そうとするんですからね。
特にひどいのは、安倍なんとかという天下一の無責任・元総理です。
菅さんが原子炉への海水注入を中止したというデマを流したんですからね。
このデマは、例によってサンケイと読売によって増幅されていきます。
デマゴーグによって時の政権を転覆させようとするんだから、恐ろしい人間です。
レベル7の原発事故が起きても、誰も死刑になったりしないこの無責任な国・日本。
その事故を利用して、権力を奪おうとする小沢一郎グループ、そして自民党。
焼け太りを企みさらに自己拡大を目指す経産省。
菅さんにはいろいろと足りない部分もあったかもしれませんが、事故の対応や、その後の脱原発への考え方とか、総合的に評価すれば立派だったと思いますよ。
菅さんが、東電の撤退を食い止めなかったら、東京(首都機能)は壊滅し、3000万人が避難することになっていたと思います。
いや、3000万人の避難なんて不可能ですから、日本は終わっていたと思います。
では、なぜあそこまで内閣支持率が低かったのかといえば、やはり原発を維持したいマスコミの報道姿勢にあったと思います。
脱原発なんて総理大臣が言ったら、引きずり下ろされちゃうんですよ、この国では。
朝日新聞だって、記者の全員が「脱原発」じゃありませんよ。
原発事故のドキュメントを書くならば、一番良い方法は菅さんに話を聞くことなんです。
なぜならば、すべての情報は菅さんのところに集まっているんだから。
そういう取材がしっかりできていたので、読み応えのある力作になっています。
この本をずっと永く保存しておいて、いずれ自分の子ども達に読ませたいなと、そんな風に思いました。
ただ余計なことを少し書いておけば専門用語がちょっと多かったかな。
「国際交渉上のバーゲニングパワーの維持」などという言葉は、義務教育を終了した人でも、ほとんどの人が理解できないと思います。
ある意味、こんなに不愉快な本はありません。
いえ、それは大鹿さんが悪いといういう意味では全然なくて、東電のあまりにも無責任な態度が不愉快なのです。
地球最大規模の福島原発事故が起きた時、東電はどうやって事故を制御すればいいか全然分かっていませんでした。
それはそうでしょう。
「事故は起きない」という「決まり」になっていたのだから、「対処法」などは存在しません。
一般の人々が、肝臓がんの手術をやれと言われても、まったく何もできないのと同じです。
東電の社長も会長も、何をどうしたらいいか意志決定ができず、ただ呆然としていたのです。
彼らが考えたのは、これ以上は危険だから原発から撤退するという決断だけでした。
泣けてくるじゃないですか。
そしてこれだけの大惨事が起きても、原発推進を貫き通そうとする経産省。
すごいですね、官僚って。
自分たちが生き残ることが自己目的になって、役所が存在するんですね。
天下りの構造なんて絶対に断ち切ることはできませんよ。
「みんなの党」が政権を取ってもそれは不可能でしょう。
政治家は、官僚がいなければ何もできないし、官僚は決して時の政権政党の味方とは限りませんからね。
しかし、恐るべきは自民党です。
経産省・東電・財界・学会と一体となって日本中に原発を作ってきて、その挙げ句、自爆したのにもかかわらず、一切責任を取らないで、これを利用して民主党政権を倒そうとするんですからね。
特にひどいのは、安倍なんとかという天下一の無責任・元総理です。
菅さんが原子炉への海水注入を中止したというデマを流したんですからね。
このデマは、例によってサンケイと読売によって増幅されていきます。
デマゴーグによって時の政権を転覆させようとするんだから、恐ろしい人間です。
レベル7の原発事故が起きても、誰も死刑になったりしないこの無責任な国・日本。
その事故を利用して、権力を奪おうとする小沢一郎グループ、そして自民党。
焼け太りを企みさらに自己拡大を目指す経産省。
菅さんにはいろいろと足りない部分もあったかもしれませんが、事故の対応や、その後の脱原発への考え方とか、総合的に評価すれば立派だったと思いますよ。
菅さんが、東電の撤退を食い止めなかったら、東京(首都機能)は壊滅し、3000万人が避難することになっていたと思います。
いや、3000万人の避難なんて不可能ですから、日本は終わっていたと思います。
では、なぜあそこまで内閣支持率が低かったのかといえば、やはり原発を維持したいマスコミの報道姿勢にあったと思います。
脱原発なんて総理大臣が言ったら、引きずり下ろされちゃうんですよ、この国では。
朝日新聞だって、記者の全員が「脱原発」じゃありませんよ。
原発事故のドキュメントを書くならば、一番良い方法は菅さんに話を聞くことなんです。
なぜならば、すべての情報は菅さんのところに集まっているんだから。
そういう取材がしっかりできていたので、読み応えのある力作になっています。
この本をずっと永く保存しておいて、いずれ自分の子ども達に読ませたいなと、そんな風に思いました。
ただ余計なことを少し書いておけば専門用語がちょっと多かったかな。
「国際交渉上のバーゲニングパワーの維持」などという言葉は、義務教育を終了した人でも、ほとんどの人が理解できないと思います。
展覧会の絵 ― 2012年04月04日 21時58分12秒
全国30万人のファンの皆様 ― 2012年04月06日 23時07分59秒
ブログはちょっとお休みします。
今朝、背筋を痛め、そのため肩凝りになってしまいました。
寄る年波には勝てません。
こんな時は休むに如かず、です。
腕が軽くなったら、再開します。
今朝、背筋を痛め、そのため肩凝りになってしまいました。
寄る年波には勝てません。
こんな時は休むに如かず、です。
腕が軽くなったら、再開します。
お陰様で ― 2012年04月07日 22時56分12秒
1日で背中の痛みは回復しました。
また、面白い本を読んだらレビューを書きましょう。
皆さん、お楽しみに。
また、面白い本を読んだらレビューを書きましょう。
皆さん、お楽しみに。
自宅となりの公園の桜 その1 ― 2012年04月08日 09時08分37秒
自宅となりの公園の桜 その2 ― 2012年04月08日 09時10分17秒
「どん底 部落差別自作自演事件」(小学館)高山 文彦 ― 2012年04月10日 21時42分08秒

これは強烈な本でした。
人間にとって最大の謎は人間、そして人間にとって最大の恐怖は人間です。
この本は、そういった人間の怖さを描いています。
ぼくは本を読んでいるうちに怖くなってしまい、背筋がゾクゾクしました。
深夜のトイレに足が向かなくなりそうになったくらいです。
最後の「付録」は正視できず、読むことができませんでした。
また、「糾弾学習会」のあり方は、大変勉強になりました。
謝罪とか、土下座を求めるのではないのですね。
その逆です。
形だけの謝罪をはねのけて、その人間の心の底の蓋を開け、中を覗き、本人にそれを直視させるのです。
だから、糾弾を受ける人間は、自分の心の底を覗く「能力」がなくてはなりません。
その能力がなければ、残念ながら、人間として高みに登ることができないのです。
本としての面白さは、高山さんの筆致もあり、重く暗く深く、単純に面白いとは言えないかもしれません。
大ベストセラーにはならないかもしれませんが、とても大事な本だと思います。
誰もが知っている有名人の評伝を書くのもノンフィクション作家の仕事ならば、誰も知らないある個人の心を描くことで、人間とはどういう生き物かを表現することも、ノンフィクション作家の重要な仕事です。
あまり話題にはなっていない作品ですが、読んで本当に良かった。
心底怖かったけど。
人間にとって最大の謎は人間、そして人間にとって最大の恐怖は人間です。
この本は、そういった人間の怖さを描いています。
ぼくは本を読んでいるうちに怖くなってしまい、背筋がゾクゾクしました。
深夜のトイレに足が向かなくなりそうになったくらいです。
最後の「付録」は正視できず、読むことができませんでした。
また、「糾弾学習会」のあり方は、大変勉強になりました。
謝罪とか、土下座を求めるのではないのですね。
その逆です。
形だけの謝罪をはねのけて、その人間の心の底の蓋を開け、中を覗き、本人にそれを直視させるのです。
だから、糾弾を受ける人間は、自分の心の底を覗く「能力」がなくてはなりません。
その能力がなければ、残念ながら、人間として高みに登ることができないのです。
本としての面白さは、高山さんの筆致もあり、重く暗く深く、単純に面白いとは言えないかもしれません。
大ベストセラーにはならないかもしれませんが、とても大事な本だと思います。
誰もが知っている有名人の評伝を書くのもノンフィクション作家の仕事ならば、誰も知らないある個人の心を描くことで、人間とはどういう生き物かを表現することも、ノンフィクション作家の重要な仕事です。
あまり話題にはなっていない作品ですが、読んで本当に良かった。
心底怖かったけど。
予測通り、大宅壮一ノンフィクション賞 ― 2012年04月11日 20時35分14秒
今年度の大宅壮一ノンフィクション賞に、「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」と「『つなみ』の子どもたち」が選ばれました。
前者に関しては2月11日のブログにこう書きました。
・・・・・・・・・・
面白いし、ベストセラーになって、話題性もあって、この本は何かの賞を取るかもしれませんね。
・・・・・・・・・・
そして後者に関しては先日、こう書きました。
・・・・・・・・・・
大宅壮一ノンフィクション賞を受賞するかもしれませんね。
・・・・・・・・・・
予測的中といった感じです。
がしかし、強調したいのは、賞を取らなかった「ホームレス歌人のいた冬」も「1985年のクラッシュ・ギャルズ」も大傑作ということです。
すべての作品がお勧めです!
前者に関しては2月11日のブログにこう書きました。
・・・・・・・・・・
面白いし、ベストセラーになって、話題性もあって、この本は何かの賞を取るかもしれませんね。
・・・・・・・・・・
そして後者に関しては先日、こう書きました。
・・・・・・・・・・
大宅壮一ノンフィクション賞を受賞するかもしれませんね。
・・・・・・・・・・
予測的中といった感じです。
がしかし、強調したいのは、賞を取らなかった「ホームレス歌人のいた冬」も「1985年のクラッシュ・ギャルズ」も大傑作ということです。
すべての作品がお勧めです!



最近のコメント