仕事と勉強にすぐに役立つ「ノート術」大全(安田 修) ― 2023年03月23日 22時51分43秒

おもしろく読みました。
ノートをどう書くかという本です。メモ術でもあります。
ぼくもノートをつけているんですよね。
手帳とは別です。
ノートの利点は多数あって、ここではすべてを書くことはできません。
この本を読んで参考になった点もあったし、ちょっと違うなと思ったこともあったし、すでに自分でやっていることもありました。
読み物としてもおもしろいので、みなさんも読んでみてはどうでしょうか。
ノートをつけると人生が変わりますよ。お勧めします。実践してみてください。
ノートをどう書くかという本です。メモ術でもあります。
ぼくもノートをつけているんですよね。
手帳とは別です。
ノートの利点は多数あって、ここではすべてを書くことはできません。
この本を読んで参考になった点もあったし、ちょっと違うなと思ったこともあったし、すでに自分でやっていることもありました。
読み物としてもおもしろいので、みなさんも読んでみてはどうでしょうか。
ノートをつけると人生が変わりますよ。お勧めします。実践してみてください。
予備費って一体なんだ? ― 2023年03月24日 22時44分34秒
国会は国権の最高機関で、多くの仕事がありますが、そのうちの一つは予算案を決めることです。
政府の出す予算案に対して意見をぶつけ合い、最終的に賛成するか反対するかが国会の重要な役割です。
ところがコロナ禍に突入し、「予備費」というものが目立つようになりました。
予算を機動的に、そして不測の事態に対応できるように作られたのだとぼくは理解しています。
しかしこういう予算執行のあり方は本当に正しいのでしょうか?
政府は物価高対策を打ち出しました。低所得の子育て世帯に子ども一人当たり5万円を給付するようです。また自治体を支援するために「地方創生臨時交付金」を出すそうです。
総額は2兆円になるようです。
コロナ対策でもこの交付金は出されましたが、コロナ対策とは関係ない無駄遣いがかなり報じられていたと思います。
今回は大丈夫なんでしょうか。
そもそもこうした予備費から交付金や物価高対策費を出すというのは、どういう理屈なんでしょうか。
なぜ、その使い道を国会で話し合わないのか?
岸田さんに5兆円の予備費があって、それが自由に使えるって、民主的と言えないのでは?
国会は機能不全を起こしていることになりませんか?
自民党の西田昌司参院議員は「自民1党でいい」と朝日新聞の取材に答えていましたが、背筋がゾッとします。
権力を握っている人たちが、他の政党は要らないと言っているのですから、これは民主国家の否定であり、独裁国家へ道を進もうとしているとか思えません。
予備費も同じです。
統一地方選が始まろうとしていますが、立憲民主党は十分な候補者を立てることができていません。
足腰が弱い状態で、政権を奪取できる可能性はないでしょう。
自民党だけがあればいい・・・、岸田さんが自由に何兆円も使える・・・、こんな悪夢は早く終わって欲しいです。
政府の出す予算案に対して意見をぶつけ合い、最終的に賛成するか反対するかが国会の重要な役割です。
ところがコロナ禍に突入し、「予備費」というものが目立つようになりました。
予算を機動的に、そして不測の事態に対応できるように作られたのだとぼくは理解しています。
しかしこういう予算執行のあり方は本当に正しいのでしょうか?
政府は物価高対策を打ち出しました。低所得の子育て世帯に子ども一人当たり5万円を給付するようです。また自治体を支援するために「地方創生臨時交付金」を出すそうです。
総額は2兆円になるようです。
コロナ対策でもこの交付金は出されましたが、コロナ対策とは関係ない無駄遣いがかなり報じられていたと思います。
今回は大丈夫なんでしょうか。
そもそもこうした予備費から交付金や物価高対策費を出すというのは、どういう理屈なんでしょうか。
なぜ、その使い道を国会で話し合わないのか?
岸田さんに5兆円の予備費があって、それが自由に使えるって、民主的と言えないのでは?
国会は機能不全を起こしていることになりませんか?
自民党の西田昌司参院議員は「自民1党でいい」と朝日新聞の取材に答えていましたが、背筋がゾッとします。
権力を握っている人たちが、他の政党は要らないと言っているのですから、これは民主国家の否定であり、独裁国家へ道を進もうとしているとか思えません。
予備費も同じです。
統一地方選が始まろうとしていますが、立憲民主党は十分な候補者を立てることができていません。
足腰が弱い状態で、政権を奪取できる可能性はないでしょう。
自民党だけがあればいい・・・、岸田さんが自由に何兆円も使える・・・、こんな悪夢は早く終わって欲しいです。
元技能実習生は死体を遺棄したのか ― 2023年03月25日 20時14分37秒
ふと気づいてみると夜のコンビニで働いているのは外国人です。
早朝の新聞配達をやる人にも外国人が多いといいます。
コンビニで売られる弁当を深夜に作っているのはだれでしょうか。これも外国人です。
日本人の多くが嫌がる単調な肉体労働は、外国人にとって代わられています。
と言うか、外国人が日本に来てくれないと、日本の産業は回っていきません。
自宅で双子を死産した後、ベトナム人の元技能実習生が、遺体を箱に納め、子どもに名前をつけて弔う言葉と共に手紙を箱に入れました。
このことが死体遺棄とされ、元実習生は起訴されて一審二審で有罪判決を受けました。
今回最高裁は、逆転無罪判決を言い渡しました。
なぜ検察は起訴をしたのでしょうか。理解に苦しみます。
元実習生が遺体を箱に納めた理由は、妊娠・出産が公になると解雇されると思っていたからです。
法的にはそういうルールはないのですが、事実上、技能実習生は退職に追い込まれることになります。
それを隠すしかなかったのです。
つまり元実習生は孤立出産にならざるを得なかったのですね。
こういう労働のあり方を「搾取」と言います。
人権をないがしろにされて、お金と交換の労働を提供し、道具として使い捨てられていたとしか言いようがありません。
日本は今後、どんどん労働力を外国人に頼らなければなりません。
ぼくだってあと25年くらいしたら、外国の方に介護してもらうかもしれません。
そのときに、日本が東南アジアの人たちにとって「搾取」されるだけの国だったら、誰も来てくれなくなっているのではないでしょうか。
孤立出産に追い込まれる女性のつらさは、想像を絶するものがあります。それも異国で。
さらに追い討ちをかけるように、司法の場で裁くという検察の論理はとても理解できません。
その論理の背後には東南アジアの人たちに対する人権的差別感情があるのではないでしょうか。
早朝の新聞配達をやる人にも外国人が多いといいます。
コンビニで売られる弁当を深夜に作っているのはだれでしょうか。これも外国人です。
日本人の多くが嫌がる単調な肉体労働は、外国人にとって代わられています。
と言うか、外国人が日本に来てくれないと、日本の産業は回っていきません。
自宅で双子を死産した後、ベトナム人の元技能実習生が、遺体を箱に納め、子どもに名前をつけて弔う言葉と共に手紙を箱に入れました。
このことが死体遺棄とされ、元実習生は起訴されて一審二審で有罪判決を受けました。
今回最高裁は、逆転無罪判決を言い渡しました。
なぜ検察は起訴をしたのでしょうか。理解に苦しみます。
元実習生が遺体を箱に納めた理由は、妊娠・出産が公になると解雇されると思っていたからです。
法的にはそういうルールはないのですが、事実上、技能実習生は退職に追い込まれることになります。
それを隠すしかなかったのです。
つまり元実習生は孤立出産にならざるを得なかったのですね。
こういう労働のあり方を「搾取」と言います。
人権をないがしろにされて、お金と交換の労働を提供し、道具として使い捨てられていたとしか言いようがありません。
日本は今後、どんどん労働力を外国人に頼らなければなりません。
ぼくだってあと25年くらいしたら、外国の方に介護してもらうかもしれません。
そのときに、日本が東南アジアの人たちにとって「搾取」されるだけの国だったら、誰も来てくれなくなっているのではないでしょうか。
孤立出産に追い込まれる女性のつらさは、想像を絶するものがあります。それも異国で。
さらに追い討ちをかけるように、司法の場で裁くという検察の論理はとても理解できません。
その論理の背後には東南アジアの人たちに対する人権的差別感情があるのではないでしょうか。
メモ活(上阪 徹) ― 2023年03月25日 21時34分36秒

メモの重要性を書いた本です。
上坂さんはなんでもメモしてそれを素材にして、素材をもとにアイデアを育てたり、書類や本を書いていきなさいと説いています。
大変おもしろく読みました。
ぼくもメモ帳とノートを使って、いろいろなことを書き留めています。
拙著『ぼくとがんの7年』はメモ帳を元に書いたようなものです。
みなさんはメモをとっていますか?
あまりとっていない? それはもったいない。
診療をしていると保護者がよく「ネットで見たんですけど・・・」と言われることがあります。
大抵は不確かの情報なんですが、それは無理もないですよね。
医療に関してアマチュアなんだから。
でも、ぼくもググりますよ。ちゃんと真偽が分かるので。
で、それをそのままにしておくのは惜しいと思います。
ぼくはググったことをノートに書き留めます。
記憶が強化されるし、もし忘れても、またググらないですみますから。
あとは、アイデアの熟成ですね。
思いついたことをノートに書き出します。書きているうちにアイデアが広がっていくんですよね。
ロジックの整理になるし、書くことで思考が促されるんです。
楽しいですよ、ノートをつけるのは。
それから、ぼくの場合、万年筆にも凝るのです。
万年筆って書いていると楽しくなんです。自宅に5本、クリニックの院長室に2本置いてあります。
この本の最後の方にブックライティングの技術が書かれていました。
あそこをもっと詳しく知りたいな。ほかの本に書いてあるのかな。ちょっと調べてみよう。
上坂さんはなんでもメモしてそれを素材にして、素材をもとにアイデアを育てたり、書類や本を書いていきなさいと説いています。
大変おもしろく読みました。
ぼくもメモ帳とノートを使って、いろいろなことを書き留めています。
拙著『ぼくとがんの7年』はメモ帳を元に書いたようなものです。
みなさんはメモをとっていますか?
あまりとっていない? それはもったいない。
診療をしていると保護者がよく「ネットで見たんですけど・・・」と言われることがあります。
大抵は不確かの情報なんですが、それは無理もないですよね。
医療に関してアマチュアなんだから。
でも、ぼくもググりますよ。ちゃんと真偽が分かるので。
で、それをそのままにしておくのは惜しいと思います。
ぼくはググったことをノートに書き留めます。
記憶が強化されるし、もし忘れても、またググらないですみますから。
あとは、アイデアの熟成ですね。
思いついたことをノートに書き出します。書きているうちにアイデアが広がっていくんですよね。
ロジックの整理になるし、書くことで思考が促されるんです。
楽しいですよ、ノートをつけるのは。
それから、ぼくの場合、万年筆にも凝るのです。
万年筆って書いていると楽しくなんです。自宅に5本、クリニックの院長室に2本置いてあります。
この本の最後の方にブックライティングの技術が書かれていました。
あそこをもっと詳しく知りたいな。ほかの本に書いてあるのかな。ちょっと調べてみよう。
紙の本はなかなか苦しい ― 2023年03月26日 20時14分14秒
出版不況と言われてから、もうだいぶ経ちます。
状況は好転する気配はなく、ますます苦しくなっているようです。
本というのは、初版に5000部印刷したとして、このうち70%くらいが売れれば損益分岐点を超えるようです。
重版になれば、それはもうお金を刷っているようなものですから、大きな利益がでます。
しかし重版になる本は書籍全体の20%くらいと聞いたことがあります。
出版不況になってから、出版点数はむしろ増えています。ま、薄利多売という感じでしょうか。村上春樹さんの本のようなメガヒットはなかなか出ないため、次から次に出版しているという具合です。
最近になって本の価格が上昇の気配を見せています。
このインフレ状況下で紙の価格も上がり、配送コストも上昇しています。
今までハードカバーで出していた本もソフトカバーになり、文庫本も600円代では買えなくなっています。
たしかに単行本1冊が1600円プラス消費税というのは、今の時代にはちょっと高額でしょう。
映画を自宅で観ようと思えば、1本2時間を400円くらいで楽しめます。
Amazonの有料会員ならば、無料動画も多数見ることが可能です。
書籍は苦しいと言えます。
電子書籍が広まると、今度は街の本屋さんが困ることになります。
やはり紙の本が売れて欲しいですね。
出版社はコスト削減に工夫を凝らすしかありません。
中央公論新社・角川春樹事務所・河出書房新社・筑摩書房の4社は文庫本の紙を共通化したそうです。
なるほど、スケールメリットが生まれますよね。
この状況を大転換する魔法のような方法はおそらくないと思います。出版社はひたすら「いい本」を作り続けることが、最良で唯一の解決策だと思います。
本好きのぼくらは、期待しながら待っています。
状況は好転する気配はなく、ますます苦しくなっているようです。
本というのは、初版に5000部印刷したとして、このうち70%くらいが売れれば損益分岐点を超えるようです。
重版になれば、それはもうお金を刷っているようなものですから、大きな利益がでます。
しかし重版になる本は書籍全体の20%くらいと聞いたことがあります。
出版不況になってから、出版点数はむしろ増えています。ま、薄利多売という感じでしょうか。村上春樹さんの本のようなメガヒットはなかなか出ないため、次から次に出版しているという具合です。
最近になって本の価格が上昇の気配を見せています。
このインフレ状況下で紙の価格も上がり、配送コストも上昇しています。
今までハードカバーで出していた本もソフトカバーになり、文庫本も600円代では買えなくなっています。
たしかに単行本1冊が1600円プラス消費税というのは、今の時代にはちょっと高額でしょう。
映画を自宅で観ようと思えば、1本2時間を400円くらいで楽しめます。
Amazonの有料会員ならば、無料動画も多数見ることが可能です。
書籍は苦しいと言えます。
電子書籍が広まると、今度は街の本屋さんが困ることになります。
やはり紙の本が売れて欲しいですね。
出版社はコスト削減に工夫を凝らすしかありません。
中央公論新社・角川春樹事務所・河出書房新社・筑摩書房の4社は文庫本の紙を共通化したそうです。
なるほど、スケールメリットが生まれますよね。
この状況を大転換する魔法のような方法はおそらくないと思います。出版社はひたすら「いい本」を作り続けることが、最良で唯一の解決策だと思います。
本好きのぼくらは、期待しながら待っています。
酔いどれクライマー 永田東一郎物語 80年代ある東大生の輝き(藤原 章生) ― 2023年03月26日 23時15分39秒
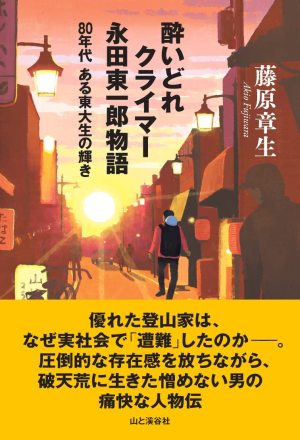
沢木耕太郎の『無名』を読んだ時に、市井に生きる平凡な人を描いても十分にノンフィクション文学になるんだなと驚きました。
これはそういう本です。
永田東一郎さんは東大生のクライマー。難峰とされるカラコルムK7の登頂に成功しますが、世間的には有名人というわけではありません。
しかし筆者にとっては、人生の中でもっとも興味を抱く人であったらしく、この「無名」なクライマーを本書で描きます。
たしかに永田さんは破格な人だったようです。自由な人だったようでもあります。臆病でもあり、チャーミングで、他人の心を読まない性格もあるようです。
少しアスペルガーなのかとも思いましたが、そういう決めつけで語れる人ではないでしょう。
ぼくにとってこの本が面白くなるのは、K7に登った後です。彼は登山をやめてしまうのですね。
その理由に関しては、筆者が4つの仮説を示しています。この分析もおもしろかった。
そして永田さんは建築士と働き始めるのですが、そこからはある意味で滑落の人生だったようにも見えます。
酒に溺れ、体を壊し、46歳の若さで亡くなります。
単にアルコール依存と言うのはちょっと違うと思います。自分でどういう人生のプランを描くか、それがうまく設計できなかったのではないでしょうか。
これは違う、
こんなはずじゃない、
本当の自分って何だ、、、
そんなことを考えていたようにぼくには感じられました。
分厚い取材と深い資料の読み込みで、一人の人間に生きた証がクリアな輪郭になりました。
その輪郭の中身には、よく見えない暗闇のようなものもありますが、評伝として一級品に仕上がったと思います。
登山に興味のない人も読んでみてください。おススメです。
これはそういう本です。
永田東一郎さんは東大生のクライマー。難峰とされるカラコルムK7の登頂に成功しますが、世間的には有名人というわけではありません。
しかし筆者にとっては、人生の中でもっとも興味を抱く人であったらしく、この「無名」なクライマーを本書で描きます。
たしかに永田さんは破格な人だったようです。自由な人だったようでもあります。臆病でもあり、チャーミングで、他人の心を読まない性格もあるようです。
少しアスペルガーなのかとも思いましたが、そういう決めつけで語れる人ではないでしょう。
ぼくにとってこの本が面白くなるのは、K7に登った後です。彼は登山をやめてしまうのですね。
その理由に関しては、筆者が4つの仮説を示しています。この分析もおもしろかった。
そして永田さんは建築士と働き始めるのですが、そこからはある意味で滑落の人生だったようにも見えます。
酒に溺れ、体を壊し、46歳の若さで亡くなります。
単にアルコール依存と言うのはちょっと違うと思います。自分でどういう人生のプランを描くか、それがうまく設計できなかったのではないでしょうか。
これは違う、
こんなはずじゃない、
本当の自分って何だ、、、
そんなことを考えていたようにぼくには感じられました。
分厚い取材と深い資料の読み込みで、一人の人間に生きた証がクリアな輪郭になりました。
その輪郭の中身には、よく見えない暗闇のようなものもありますが、評伝として一級品に仕上がったと思います。
登山に興味のない人も読んでみてください。おススメです。
本当に怖い学術会議改革案 ― 2023年03月27日 19時23分21秒
国家権力が学術に手を突っ込んでくるのは大変危険なことです。
日本の戦後復興には多くの要因があったと思いますが、そのうちの一つには学問に(これまでは)お金を注ぎ込んできたことが挙げられると思います。
いや、お金ではなく、優秀な日本人が自由に研究をしたからかもしれません。
湯川秀樹さんのノーベル物理学賞は、なんと1949年です。戦後すぐですよね。
こうした学問の積み重ねが今日の日本を作ってきたのでしょう。それは文系も理系も同様です。
菅前首相は、2020年に学術会議から推薦された105人のうち6人を任命しませんでした。その6人は、政府に対しても直言することのある学者でした。
当然、メディアや野党は「批判的な学者を排除する意図ではないか」と追求しましたが、菅さんは理由を語りませんでした。
理由を語らないってありですか?
これは民主国家の姿ではありません。
その後、岸田首相は「それは済んだ話。一連の手続きは終了した」と、なぜ済んだのか一切説明しません。
こんな政治の姿が許されるのでしょうか?
説明しない政治は、恐ろしいとしか言いようがありません。
学術会議のメンバーを決める新しいシシテムとして第三者が関与する法案を政府は用意しています。
でも、その第三者を決めるのは政府ですよね。
これは相当ヤバいのではないでしょうか?
そんなことをしている国は世界にはありません。
学術会議の会員は、会議の内部で選考して決めています。つまり、学問は政府と独立して存在し、自由に学問を進めているのです。
日本はどうしてこういう「世界標準」と異なることばかりをするのでしょうか?
右翼の人たちは、こうした自民党政権のやり方に賛同していますが、こうした道を進めば進むほど、日本は世界から笑いものになっていきます。
国際的に名誉ある地位にいて、世界から尊敬される国になろうという意思はないのでしょうか?
学術会議改革案が国会で可決されれば、学問の自由は失われ、「御用学者」が増えていくことになります。
メディアは厳しくこの問題をチェックしてください。
もちろん、リベラル野党は、この問題を激しく追求してください。
学問の独立と自由が侵されることは、本当に危険なこと、そして日本がこれからさらに衰退していく道につながると考えておく必要があります。
日本の戦後復興には多くの要因があったと思いますが、そのうちの一つには学問に(これまでは)お金を注ぎ込んできたことが挙げられると思います。
いや、お金ではなく、優秀な日本人が自由に研究をしたからかもしれません。
湯川秀樹さんのノーベル物理学賞は、なんと1949年です。戦後すぐですよね。
こうした学問の積み重ねが今日の日本を作ってきたのでしょう。それは文系も理系も同様です。
菅前首相は、2020年に学術会議から推薦された105人のうち6人を任命しませんでした。その6人は、政府に対しても直言することのある学者でした。
当然、メディアや野党は「批判的な学者を排除する意図ではないか」と追求しましたが、菅さんは理由を語りませんでした。
理由を語らないってありですか?
これは民主国家の姿ではありません。
その後、岸田首相は「それは済んだ話。一連の手続きは終了した」と、なぜ済んだのか一切説明しません。
こんな政治の姿が許されるのでしょうか?
説明しない政治は、恐ろしいとしか言いようがありません。
学術会議のメンバーを決める新しいシシテムとして第三者が関与する法案を政府は用意しています。
でも、その第三者を決めるのは政府ですよね。
これは相当ヤバいのではないでしょうか?
そんなことをしている国は世界にはありません。
学術会議の会員は、会議の内部で選考して決めています。つまり、学問は政府と独立して存在し、自由に学問を進めているのです。
日本はどうしてこういう「世界標準」と異なることばかりをするのでしょうか?
右翼の人たちは、こうした自民党政権のやり方に賛同していますが、こうした道を進めば進むほど、日本は世界から笑いものになっていきます。
国際的に名誉ある地位にいて、世界から尊敬される国になろうという意思はないのでしょうか?
学術会議改革案が国会で可決されれば、学問の自由は失われ、「御用学者」が増えていくことになります。
メディアは厳しくこの問題をチェックしてください。
もちろん、リベラル野党は、この問題を激しく追求してください。
学問の独立と自由が侵されることは、本当に危険なこと、そして日本がこれからさらに衰退していく道につながると考えておく必要があります。
史上最低の予算案成立 ― 2023年03月28日 20時07分43秒
2023年度の予算案が成立しました。
自民党国対によれば「あっという間に成立してしまった」そうです。
今の野党は審議を引き延ばしたりしませんので、とんとん拍子だったのでしょう。
ですが、熟議が形成されたとは言えないと思います。
岸田さんは、やれ検討するだの、今後叩き台を提示するだの、国会の場で議論しようとしません。
議論が深まらないのは、岸田さんの責任です。
防衛費は26%増加し、子育て関連予算はわずか2.6%しか増えていません。
本当にそれでいいのでしょうか?
お隣の韓国は過去何十年にもわたって時の政権が反日感情を利用し、あるいは煽って、政権浮揚を図ることを繰り返していました。
しかしこれは日本も同じです。
国民を一つにまとめる方法は簡単で、いま、そこに危機があり外国が戦争を仕掛けようとしていると煽ればいいのです。
平和主義者やリベラルな人間を潰すのは簡単で、あの連中には愛国心がないと宣伝すればいいのです。
世界の歴史は、自国民の愛国心を煽ることの繰り返しでした。
「愛国心とはならず者の最後の逃げ場」という言葉がありますが、本当にその通りだと思います。
敵基地攻撃とか、トマホーク2000発とか、本当に必要なんでしょうか?
では、日米安保は何のために存在しているのでしょうか?
岸田さんが首相になってとき、「令和版所得倍増」とか「民主主義の危機」とか「聞く力」とか言っていました。
ところがやっていることは、超国家主義の反動政治です。
アベノマスクの単価が裁判を経て開示されることになりましたが、そもそもなぜこれが秘密なんですか?
政権の秘密主義には恐怖さえ感じます。
子どもから首相を目指した理由を聞かれて、岸田さんは「日本の社会のなかで一番、権限の大きい人なので目指した」と答えています。
恐ろしいじゃないですか?
過去にそんなことを言った総理大臣っていました?
思っても普通は言わないと思いますよ。
権力欲にゴリゴリに凝り固まった男が、政権を維持できればどんな手段でも使うというのは、我が祖国にとって悪夢でしかありません。
この悪夢から少しでも醒めることを祈るばかりです。
自民党国対によれば「あっという間に成立してしまった」そうです。
今の野党は審議を引き延ばしたりしませんので、とんとん拍子だったのでしょう。
ですが、熟議が形成されたとは言えないと思います。
岸田さんは、やれ検討するだの、今後叩き台を提示するだの、国会の場で議論しようとしません。
議論が深まらないのは、岸田さんの責任です。
防衛費は26%増加し、子育て関連予算はわずか2.6%しか増えていません。
本当にそれでいいのでしょうか?
お隣の韓国は過去何十年にもわたって時の政権が反日感情を利用し、あるいは煽って、政権浮揚を図ることを繰り返していました。
しかしこれは日本も同じです。
国民を一つにまとめる方法は簡単で、いま、そこに危機があり外国が戦争を仕掛けようとしていると煽ればいいのです。
平和主義者やリベラルな人間を潰すのは簡単で、あの連中には愛国心がないと宣伝すればいいのです。
世界の歴史は、自国民の愛国心を煽ることの繰り返しでした。
「愛国心とはならず者の最後の逃げ場」という言葉がありますが、本当にその通りだと思います。
敵基地攻撃とか、トマホーク2000発とか、本当に必要なんでしょうか?
では、日米安保は何のために存在しているのでしょうか?
岸田さんが首相になってとき、「令和版所得倍増」とか「民主主義の危機」とか「聞く力」とか言っていました。
ところがやっていることは、超国家主義の反動政治です。
アベノマスクの単価が裁判を経て開示されることになりましたが、そもそもなぜこれが秘密なんですか?
政権の秘密主義には恐怖さえ感じます。
子どもから首相を目指した理由を聞かれて、岸田さんは「日本の社会のなかで一番、権限の大きい人なので目指した」と答えています。
恐ろしいじゃないですか?
過去にそんなことを言った総理大臣っていました?
思っても普通は言わないと思いますよ。
権力欲にゴリゴリに凝り固まった男が、政権を維持できればどんな手段でも使うというのは、我が祖国にとって悪夢でしかありません。
この悪夢から少しでも醒めることを祈るばかりです。
母は死ねない(河合 香織) ― 2023年03月29日 09時08分06秒
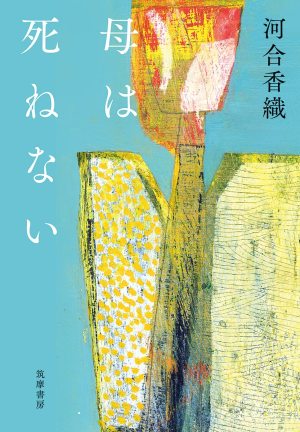
筆者の河合香織さんが産科的 DIC に陥り、死にかける話から始まります。
子どもを産んだときに、敗血症ショックで命が危なかったことは、ご本人から聞いたことがありましたが、実際に詳細を本で読んでみると、その緊迫感は並大抵のレベルではなかったと痛感しました。
ガリガリ君を食べる場面では生きることへの執着が迸り出ていて、本当に「母は死ねない」のだなと心底思いました。
そう、この本のタイトルは「母は死ねない」です。
多くの母親たちが登場し、子どもを欲しいと思うこと、子どもを授かること、子どもを失うこと、子どもを愛おしいと思うことが綴られていきます。
体裁はエッセイに見えますが、手法はノンフィクション(ルポルタージュ)であり、表現はリリカルで、触れれば血が滲みそうな繊細な短編集となっています。
母親と父親では、子どもとの関係性において少し違いがあることは言っておかなければなりません。
やはり産むのは母親だからでしょう。
「母は死ねない」という出だしから本作はスタートしますが、読んでいるうち、それが少しずつ揺らいでいきます。
母は愛おしく、悲しく、切なく、尊く・・・そして「母は死ねない」という宿命論的な呪縛は、もしかしたら幻かもしれません。
母には、自分の母親との関係においても、自分の子どもとの関係においても、実はもう少し自由なのかもしれません。
ただ、母として生きると、「死ねない」「ねばならない」という位置に押し込まれてしまうのでしょう。
最後まで読み終えるとタイトルに反して、「母は死ねない」と思わないでいいと河合さんは、母親たちに赦しのような言葉をかけているように思えます。
文学的香りに満ちた美しい作品でした。
ぜひ、読んでみてください。
子どもを産んだときに、敗血症ショックで命が危なかったことは、ご本人から聞いたことがありましたが、実際に詳細を本で読んでみると、その緊迫感は並大抵のレベルではなかったと痛感しました。
ガリガリ君を食べる場面では生きることへの執着が迸り出ていて、本当に「母は死ねない」のだなと心底思いました。
そう、この本のタイトルは「母は死ねない」です。
多くの母親たちが登場し、子どもを欲しいと思うこと、子どもを授かること、子どもを失うこと、子どもを愛おしいと思うことが綴られていきます。
体裁はエッセイに見えますが、手法はノンフィクション(ルポルタージュ)であり、表現はリリカルで、触れれば血が滲みそうな繊細な短編集となっています。
母親と父親では、子どもとの関係性において少し違いがあることは言っておかなければなりません。
やはり産むのは母親だからでしょう。
「母は死ねない」という出だしから本作はスタートしますが、読んでいるうち、それが少しずつ揺らいでいきます。
母は愛おしく、悲しく、切なく、尊く・・・そして「母は死ねない」という宿命論的な呪縛は、もしかしたら幻かもしれません。
母には、自分の母親との関係においても、自分の子どもとの関係においても、実はもう少し自由なのかもしれません。
ただ、母として生きると、「死ねない」「ねばならない」という位置に押し込まれてしまうのでしょう。
最後まで読み終えるとタイトルに反して、「母は死ねない」と思わないでいいと河合さんは、母親たちに赦しのような言葉をかけているように思えます。
文学的香りに満ちた美しい作品でした。
ぜひ、読んでみてください。
タオルで胸隠し健診へ ― 2023年03月30日 19時59分40秒
小学校や中学校の学校健診で、女子が上半身裸になることに対して不安や不満の声がいろいろなところから上がっています。
この対応策として京都府長岡京市教育委員会は、2023年度から、内科健診の際にタオルで胸を隠し、必要に応じてめくり上げる方法を全校で取り入れることに決めたそうです。
ぼくも千葉市内の小学校の校医を務めていますが、小学3年以上は、上半身着衣(体操着)のまま健診をやっています。
聴診が必要な場合は、服の下から聴診器を差し込んでいます。
長岡市には「子どもたちの安心できる健康診断をめざす会」というものがあって、下着などを着けたまま健診を受けられるよう求める約5300筆の署名を市教委に提出したそうです。
今回の対応を少しは評価したようですが、保護者からは「異性の医師に胸を見せないといけない状況は変わらず残念」という意見もあるそうです。
ぼくにはいい案があります。
まず、胸を見られることが嫌ならば学校を休めばいいだけのことです。
子どもが嫌がるのに、なぜ親は健診に行かせるのでしょうか?
ぼくにはその理由がさっぱり分かりません。
「嫌ならやめろ」とぼくは言いたいです。
そしてもっと根本的な解決策があります。
それは健診それ自体をやめることです。
昭和の貧困な時代は終わりました。子どもたちは基本的にみんな健康です。
何か病的なものが見つかっても、ほぼ100%の子はすでに医療機関で診てもらっています。
それに、何か重篤な病気が1〜2分の健診で見つかることなんてないでしょう。
要らないんじゃないですか?
側湾症とかのチェックは、自宅でやったらどうでしょう?
保護者にチェック項目を教えれば十分です。
それに軽度の側湾症は画像検査をやらなければ見つかりません。
年に1回健診をするよりも、普段から親がちゃんと見ている方がよっぽど診断的に優れています。
漏斗胸だって同じです。
学校医という仕事は、医師としての義務感でやっているものです。
好きでやっているわけではない。
貴重な一日を健診でつぶされ、しかたなくやっているわけです。
これは医師にとって医師会から要請される義務です。
それを「異性の医師に胸を見られたくない」とか言われると不愉快でしかありません。
嫌ならやめてください。
この対応策として京都府長岡京市教育委員会は、2023年度から、内科健診の際にタオルで胸を隠し、必要に応じてめくり上げる方法を全校で取り入れることに決めたそうです。
ぼくも千葉市内の小学校の校医を務めていますが、小学3年以上は、上半身着衣(体操着)のまま健診をやっています。
聴診が必要な場合は、服の下から聴診器を差し込んでいます。
長岡市には「子どもたちの安心できる健康診断をめざす会」というものがあって、下着などを着けたまま健診を受けられるよう求める約5300筆の署名を市教委に提出したそうです。
今回の対応を少しは評価したようですが、保護者からは「異性の医師に胸を見せないといけない状況は変わらず残念」という意見もあるそうです。
ぼくにはいい案があります。
まず、胸を見られることが嫌ならば学校を休めばいいだけのことです。
子どもが嫌がるのに、なぜ親は健診に行かせるのでしょうか?
ぼくにはその理由がさっぱり分かりません。
「嫌ならやめろ」とぼくは言いたいです。
そしてもっと根本的な解決策があります。
それは健診それ自体をやめることです。
昭和の貧困な時代は終わりました。子どもたちは基本的にみんな健康です。
何か病的なものが見つかっても、ほぼ100%の子はすでに医療機関で診てもらっています。
それに、何か重篤な病気が1〜2分の健診で見つかることなんてないでしょう。
要らないんじゃないですか?
側湾症とかのチェックは、自宅でやったらどうでしょう?
保護者にチェック項目を教えれば十分です。
それに軽度の側湾症は画像検査をやらなければ見つかりません。
年に1回健診をするよりも、普段から親がちゃんと見ている方がよっぽど診断的に優れています。
漏斗胸だって同じです。
学校医という仕事は、医師としての義務感でやっているものです。
好きでやっているわけではない。
貴重な一日を健診でつぶされ、しかたなくやっているわけです。
これは医師にとって医師会から要請される義務です。
それを「異性の医師に胸を見られたくない」とか言われると不愉快でしかありません。
嫌ならやめてください。



最近のコメント