つんくの「生きる選択」に涙 ― 2015年04月04日 20時28分49秒
詳しく知っている人ではありませんが、その昔、「シングルベッド」「ズルい女」という曲を聞いた時にとても才能のある歌手(アーティスト)と思ったものです。
その彼が、喉頭がんによって手術で声を失ったそうです。
近畿大学の入学式で、しっかりとしたメッセージを伝えたと報道されていました。
ネットのニュースをぱらりぱらりと読んでいると、早くも、つんくの「生きる選択」に涙とか感動とかいう言葉が並んでいます。
そうした心情はぼくも理解できますが、ま、ちょっと待ってください。
喉頭がんになれば、(病期によりますが)手術で喉頭を摘出するのは当然の治療手段です。
彼は初回治療を終えてすぐに再発していましたから、化学療法や放射線療法がまったく効かなかったということです。
効かなかった理由は、がんの悪性度が高かったか、病期が進みすぎていたのかのどちらかです。
そうなると当然手術になります。
手術しなければ、命はない訳ですので、そうした「選択」をすること自体は誰もが選ぶ道だと思います。手術しなければ、たとえ気管切開しても、がんが進んで窒息する危険すらあります。
だから彼の「選択」が立派だということではない。
同じような人は世界中にいくらでもいます。
つんくが立派なのは(朝日新聞で読んだのですが)、彼の近畿大学生へのメッセージにあります。
「後悔しても意味は無い」
これだと思います。
人生とは思い通りにいかず、不条理な苦痛に苛まれて、絶望の渕に立たされたりします。
しかし、人がいくら人生に絶望しても、人生はその人に絶望することなく、いくらでもその人に付いてくるのです。
であれば、どういう環境に生きても、人は自分で人生を作っていくしかありません。
そういう意味で彼は立派だと思います。
さて、つんくさんがタバコを吸っていたかどうか僕は知りませんが、常識的に考えれば喉頭がんの原因はタバコです。
タバコには60種類以上の発がん物質が含まれています。
こんなものは、さっさと法律で禁止すべきです。
その彼が、喉頭がんによって手術で声を失ったそうです。
近畿大学の入学式で、しっかりとしたメッセージを伝えたと報道されていました。
ネットのニュースをぱらりぱらりと読んでいると、早くも、つんくの「生きる選択」に涙とか感動とかいう言葉が並んでいます。
そうした心情はぼくも理解できますが、ま、ちょっと待ってください。
喉頭がんになれば、(病期によりますが)手術で喉頭を摘出するのは当然の治療手段です。
彼は初回治療を終えてすぐに再発していましたから、化学療法や放射線療法がまったく効かなかったということです。
効かなかった理由は、がんの悪性度が高かったか、病期が進みすぎていたのかのどちらかです。
そうなると当然手術になります。
手術しなければ、命はない訳ですので、そうした「選択」をすること自体は誰もが選ぶ道だと思います。手術しなければ、たとえ気管切開しても、がんが進んで窒息する危険すらあります。
だから彼の「選択」が立派だということではない。
同じような人は世界中にいくらでもいます。
つんくが立派なのは(朝日新聞で読んだのですが)、彼の近畿大学生へのメッセージにあります。
「後悔しても意味は無い」
これだと思います。
人生とは思い通りにいかず、不条理な苦痛に苛まれて、絶望の渕に立たされたりします。
しかし、人がいくら人生に絶望しても、人生はその人に絶望することなく、いくらでもその人に付いてくるのです。
であれば、どういう環境に生きても、人は自分で人生を作っていくしかありません。
そういう意味で彼は立派だと思います。
さて、つんくさんがタバコを吸っていたかどうか僕は知りませんが、常識的に考えれば喉頭がんの原因はタバコです。
タバコには60種類以上の発がん物質が含まれています。
こんなものは、さっさと法律で禁止すべきです。
こころの時代 禅僧ティク・ナット・ハン ― 2015年04月05日 15時11分44秒
NHK Eテレで、「こころの時代 禅僧ティク・ナット・ハン」を視聴しました。
テーマは怒りの炎を抱きしめて、怒りを変容させることです。
ハン師は、若き日にベトナム戦争で多くの怒り・悲しみ・嘆きを体験しました。
そして自分の中にある怒りを見詰め、それを抱きとめるように「面倒」を見て、静かにさせました。
差別や憎悪もたくさん経験してきましたが、ハン師は、苦しみとは闘いません。
そういった自分の中の負の感情を、理解して慈悲の高さまで持ち上げるのです。
ですから、怒りに燃えた敵がいたとしても、その敵に対して怒りで対決することはありません。
怒りに燃えた敵は哀れな人なので、その敵を慈悲で包んでしまうのです。
ハン師がキング牧師と共鳴したというのはとてもよく理解できます。
が、しかしここでもハン師は、「戦友」であるキング牧師を暗殺という悲劇で失うという苦しみを味わうことになります。
人はどうしたら怒りの炎を抱きしめることができるのでしょうか?
それにはまず、自分が自分という一つの存在であるということを自覚することから始まります。
一つ、息を吸って、瞑想し、自分の存在を知る。
自分を知れば、他者を知ることができる。
自分の持っている庭をきれいにすることが可能ならば、そこで初めて他人の庭をきれいにすることができるようになる。
そして、自分は孤立した存在なのではなく、人によって生かされている相互共存の中にいると知ります。
自分が人と共にある。
そうであれば、怒りに対して怒りで対抗しても何の意味もありません。
ベトナムで5人の子どもを殺したことに苦悩するアメリカ人帰還兵。彼に対して、ベトナム人が糾弾しても何も変わらない。
しかしもし、明日から毎日、子どもの命を5人、10人、15人と救いなさいとベトナム人が言ったらどうでしょうか?
世界には一粒の薬が無くて命を失っていく子どもが無数にいます。
そのベトナム帰還兵のすべきことは、ベトナム人に赦しを乞うことではなく、子どもの命を救うという「実践」だったのです。
・・・・・・・・・・・・・・・
さすがNHKですね。素晴らしい番組でした。
ぼくは若い日にマルコムXから強い影響を受けました。
マルコムXの教えは「いかなる手段をとろうとも」ですから、ハン師とはかなり異なっているかもしれません。
ですが、ハン師・キング牧師・マルコムXが最終的に夢見た未来社会はとても似ていたのだと思います。
なお、ぼくは修行が全然足りなくて、世の中に不条理な差別があると、やはり怒りが湧き上がってきてしまいます。
しかし、この番組をきっかけに怒りとはなんだろうと深く考えてみたいです。
テーマは怒りの炎を抱きしめて、怒りを変容させることです。
ハン師は、若き日にベトナム戦争で多くの怒り・悲しみ・嘆きを体験しました。
そして自分の中にある怒りを見詰め、それを抱きとめるように「面倒」を見て、静かにさせました。
差別や憎悪もたくさん経験してきましたが、ハン師は、苦しみとは闘いません。
そういった自分の中の負の感情を、理解して慈悲の高さまで持ち上げるのです。
ですから、怒りに燃えた敵がいたとしても、その敵に対して怒りで対決することはありません。
怒りに燃えた敵は哀れな人なので、その敵を慈悲で包んでしまうのです。
ハン師がキング牧師と共鳴したというのはとてもよく理解できます。
が、しかしここでもハン師は、「戦友」であるキング牧師を暗殺という悲劇で失うという苦しみを味わうことになります。
人はどうしたら怒りの炎を抱きしめることができるのでしょうか?
それにはまず、自分が自分という一つの存在であるということを自覚することから始まります。
一つ、息を吸って、瞑想し、自分の存在を知る。
自分を知れば、他者を知ることができる。
自分の持っている庭をきれいにすることが可能ならば、そこで初めて他人の庭をきれいにすることができるようになる。
そして、自分は孤立した存在なのではなく、人によって生かされている相互共存の中にいると知ります。
自分が人と共にある。
そうであれば、怒りに対して怒りで対抗しても何の意味もありません。
ベトナムで5人の子どもを殺したことに苦悩するアメリカ人帰還兵。彼に対して、ベトナム人が糾弾しても何も変わらない。
しかしもし、明日から毎日、子どもの命を5人、10人、15人と救いなさいとベトナム人が言ったらどうでしょうか?
世界には一粒の薬が無くて命を失っていく子どもが無数にいます。
そのベトナム帰還兵のすべきことは、ベトナム人に赦しを乞うことではなく、子どもの命を救うという「実践」だったのです。
・・・・・・・・・・・・・・・
さすがNHKですね。素晴らしい番組でした。
ぼくは若い日にマルコムXから強い影響を受けました。
マルコムXの教えは「いかなる手段をとろうとも」ですから、ハン師とはかなり異なっているかもしれません。
ですが、ハン師・キング牧師・マルコムXが最終的に夢見た未来社会はとても似ていたのだと思います。
なお、ぼくは修行が全然足りなくて、世の中に不条理な差別があると、やはり怒りが湧き上がってきてしまいます。
しかし、この番組をきっかけに怒りとはなんだろうと深く考えてみたいです。
怒りの面倒をみる ― 2015年04月10日 11時12分26秒
人生の恩人とも言うべき人から、貴重な助言を頂きました。
その内容を、直接話法の形でなく、自分流にアレンジして書いてみます。
この世の中には不条理なこと、苦痛なこと、理不尽なこと、不正なことが山ほどあります。
社会全体もそうだし、あなたが所属する会社もそうでしょう。
ぼくが所属していた大学病院もそうだし、「医局」もそうです。
そういった仕組みや制度を改革したいと思っても、それは大変困難です。社会は容易には変わらないのです。
であれば、発想を変えて自分を変えてみてはどうか?
自分がよりよい人間になっていくことで、周囲に影響を及ぼし、社会が変わる可能性があります。
ま、ちょっと意訳かもしれませんがそういうことを学びました。
この「変わる」というのはなかなか難しく、信念を捨てることがあってはいけない。
社会によって個人が変化させられてはいけません。そうした強さは保持する必要があります。
しかし、自分の欠けているもの、不十分なものがあれば、それらを乗り越えていくべきでしょう。
ぼくに足りないもの。それは「赦す」心です。
明らかに自分の欠陥だと思います。
なぜ、「赦し」の気持ちが弱いのか?
それはおそらく、ぼくは自分を肯定することができないので、人間として弱いのでしょう。
今までの長い人生を振り返ると、ぼくは節目節目で他者から否定されてきた。
それも、ぼく自分にはどうにもできない、ぼくの本質とは関係ない属性を問題にされて否定されてきたと感じます。
ティク・ナット・ハン師は、怒りの面倒を見て、怒りを変容します。
ぼくにはこれができない。
障害児が差別されていたり、在日に対するヘイトスピーチを聞いたり、被差別部落の人が不当な扱いを受けたり、性的少数派が疎外されたり、そういうものを見ると「怒り」が湧きます。
しかし、怒りとは本当に面倒をみなければいけないものなのでしょうか?
「私怨」という言葉があります。個人的な恨みですね。
ですが、「公憤」という言葉だってある。
怒りにも、下品なものと美しいものがあるのではないでしょうか?
「青い芝の会」だって「部落解放同盟」だってマルコムXだって怒っていました。
その結果、社会は大きく変わった訳です。
だから、個人の利害を超越した怒りは大事にしてもいいのではないか?
社会を変えるためにまず、自分が変わる。
そのためにぼくは、「私怨」と「公憤」を切り分けて、自分の自由を束縛する「私怨」に基づいた頑迷な観念から離れる必要がありそうです。
そうすれば自分は、少しでもましな人間になって、ぼくの声は少しでも力を得ることが可能かもしれません。
命が果てるまで、まだもうちょっと時間がありそうです。
少しずつ前進したいと思います。
その内容を、直接話法の形でなく、自分流にアレンジして書いてみます。
この世の中には不条理なこと、苦痛なこと、理不尽なこと、不正なことが山ほどあります。
社会全体もそうだし、あなたが所属する会社もそうでしょう。
ぼくが所属していた大学病院もそうだし、「医局」もそうです。
そういった仕組みや制度を改革したいと思っても、それは大変困難です。社会は容易には変わらないのです。
であれば、発想を変えて自分を変えてみてはどうか?
自分がよりよい人間になっていくことで、周囲に影響を及ぼし、社会が変わる可能性があります。
ま、ちょっと意訳かもしれませんがそういうことを学びました。
この「変わる」というのはなかなか難しく、信念を捨てることがあってはいけない。
社会によって個人が変化させられてはいけません。そうした強さは保持する必要があります。
しかし、自分の欠けているもの、不十分なものがあれば、それらを乗り越えていくべきでしょう。
ぼくに足りないもの。それは「赦す」心です。
明らかに自分の欠陥だと思います。
なぜ、「赦し」の気持ちが弱いのか?
それはおそらく、ぼくは自分を肯定することができないので、人間として弱いのでしょう。
今までの長い人生を振り返ると、ぼくは節目節目で他者から否定されてきた。
それも、ぼく自分にはどうにもできない、ぼくの本質とは関係ない属性を問題にされて否定されてきたと感じます。
ティク・ナット・ハン師は、怒りの面倒を見て、怒りを変容します。
ぼくにはこれができない。
障害児が差別されていたり、在日に対するヘイトスピーチを聞いたり、被差別部落の人が不当な扱いを受けたり、性的少数派が疎外されたり、そういうものを見ると「怒り」が湧きます。
しかし、怒りとは本当に面倒をみなければいけないものなのでしょうか?
「私怨」という言葉があります。個人的な恨みですね。
ですが、「公憤」という言葉だってある。
怒りにも、下品なものと美しいものがあるのではないでしょうか?
「青い芝の会」だって「部落解放同盟」だってマルコムXだって怒っていました。
その結果、社会は大きく変わった訳です。
だから、個人の利害を超越した怒りは大事にしてもいいのではないか?
社会を変えるためにまず、自分が変わる。
そのためにぼくは、「私怨」と「公憤」を切り分けて、自分の自由を束縛する「私怨」に基づいた頑迷な観念から離れる必要がありそうです。
そうすれば自分は、少しでもましな人間になって、ぼくの声は少しでも力を得ることが可能かもしれません。
命が果てるまで、まだもうちょっと時間がありそうです。
少しずつ前進したいと思います。
プロ野球 最強の助っ人論 (講談社現代新書) 中島 国章 ― 2015年04月13日 20時36分41秒

面白い話が多々ありましたが、本としてのできはどうでしょうか?
必要以上に「繰り返し・重複」があり、個々のエピソードが全体として一つの流れになっていないような印象があります。
必要以上に「繰り返し・重複」があり、個々のエピソードが全体として一つの流れになっていないような印象があります。
「聞き出す力」吉田 豪 ― 2015年04月13日 20時40分09秒
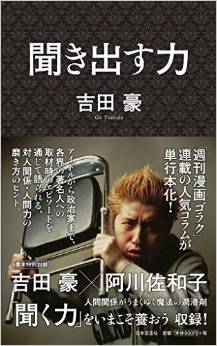
ぼくも仕事で「聞き出す」ことをしますので、勉強のつもりで読みました。
吉田さんならでは作品と思います。
ただ、文章の力で読ませる本ではないから、そんなことはどうでもいいのかもしれませんが、「読ませる力」にはちょっと疑問がありました。
吉田さんならでは作品と思います。
ただ、文章の力で読ませる本ではないから、そんなことはどうでもいいのかもしれませんが、「読ませる力」にはちょっと疑問がありました。
「悪役レスラーのやさしい素顔」ミスター高橋 ― 2015年04月13日 20時45分56秒
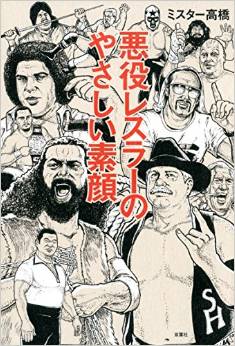
これは面白かった。
若干、編集が甘くて、「繰り返し・重複」がありましたが、ま、いいでしょう。
猪木にとって最も重要な外国人レスラーは、シンとハンセンですが、ハンセンのページが非常に短いのはどうした訳でしょうか?
ここだけが物足りなかったです。
若干、編集が甘くて、「繰り返し・重複」がありましたが、ま、いいでしょう。
猪木にとって最も重要な外国人レスラーは、シンとハンセンですが、ハンセンのページが非常に短いのはどうした訳でしょうか?
ここだけが物足りなかったです。
「無銭横町」西村 賢太 ― 2015年04月14日 21時33分39秒
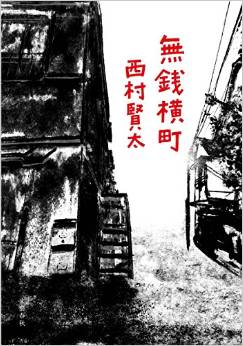
安定していますね。
ここまで予定調和だと、面白いのか、面白くないのか、よく分かりません。
次の作品が出たら? もちろん買います。
ここまで予定調和だと、面白いのか、面白くないのか、よく分かりません。
次の作品が出たら? もちろん買います。
「出生前診断 出産ジャーナリストが見つめた現状と未来」 (朝日新書) 河合 蘭 ― 2015年04月15日 00時04分51秒

大変な力作だと思います。
出生前診断に関するほぼすべての情報が詰まっていると思います。
DNAを肉眼で見た経験もなければ、(おそらく)帝王切開の場面を生で見た経験のないジャーナリストがよくここまで書けたなと(皮肉でなしに)感心します。
ただ、障害胎児に対する考えの基盤は、ぼくとこの著者さんとではまったく異なっているので、ぼくが同じテーマで本を書いたら全然違うものができると思います。
出生前診断に関するほぼすべての情報が詰まっていると思います。
DNAを肉眼で見た経験もなければ、(おそらく)帝王切開の場面を生で見た経験のないジャーナリストがよくここまで書けたなと(皮肉でなしに)感心します。
ただ、障害胎児に対する考えの基盤は、ぼくとこの著者さんとではまったく異なっているので、ぼくが同じテーマで本を書いたら全然違うものができると思います。
禅僧ティク・ナット・ハン 「死は存在しない」 ― 2015年04月18日 14時26分47秒
禅僧ティク・ナット・ハン 第2回の放送を見ました。
今回の番組は3つのパートからできていました。
前半は、マインドフルネス=いま、ここに気づくこと。
悲しみも、苦しみも、怒りも、否定する必要はない。
誰にでも孤独や悩みが訪れる。
そんなときに、自分自身が存在することを意識する。
いま、ここに自分があるということに気づけばいい。そうすれば他者も存在するということに自然と気づき、私という存在は突き放された孤独なものでないと知る。
中盤は、師に影響を受けたいろいろな人が登場していました。
彼ら・彼女らは、ハン師によって、新しい気づきの中にいる。
何かを知ったとき、人は幸せを感じることができるでしょう。
そういう表情をしていました。
だけどさすがに、ハン師が見せる独特な「はにかむ」ような笑顔、ちょっとかすれた声で分かりやすい単語を駆使した音楽の旋律のような英語と比べると、ちょっと勝てないかなと感じます。
ハン師は、本当に存在そのものが慈愛に満ちていますね。
終盤は、「死は存在しない」ということ。
ここの部分は、従来からのぼくの主張とまったく同じです。
拙著「小児がん外科医」で、がんで死んでいく何人もの子どもの死を描きました。
研修医の頃のぼくは、「死」は痛みであり、恐怖であり、暗闇であり、悲しみであると思っていました。
そして医師にとって、「子どもの死」は敗北だと思っていた訳です。
だけどたくさんの子どもの死を見る中で、それは間違ったイメージと知りました。
ぼくは「死後の世界」が存在するとか、「霊魂」が存在すると主張している訳ではありません。
ある一点で、何かがブツッと断絶してしまう「死」は存在しない。
子どもの肉体が見えなくなっても、家族の形は決して崩れない。
死に立ち向かった家族は、子どもの死のあとも、その子を含めて家族としての歩みを続けていくのです。
決して、恐怖でもなければ敗北でもありません。
ぼくは死を迎えた子どもの母親に、「死は存在しません」と言い切ったことがあります。
中央公論新社の「小児がん外科医」は大して売れていませんが、このたび、愛媛県の高校生の道徳の授業のサブテキストに、拙著の一部が採録されました。
「死は存在しない」というタイトルの一章です。
ハン師の思想とぼくの雑感を比べるのもおこがましい話ですが、何十人もの子どもの死を見た経験から得た結論が「死は存在しない」ということです。
素晴らしい番組でした。
今回の番組は3つのパートからできていました。
前半は、マインドフルネス=いま、ここに気づくこと。
悲しみも、苦しみも、怒りも、否定する必要はない。
誰にでも孤独や悩みが訪れる。
そんなときに、自分自身が存在することを意識する。
いま、ここに自分があるということに気づけばいい。そうすれば他者も存在するということに自然と気づき、私という存在は突き放された孤独なものでないと知る。
中盤は、師に影響を受けたいろいろな人が登場していました。
彼ら・彼女らは、ハン師によって、新しい気づきの中にいる。
何かを知ったとき、人は幸せを感じることができるでしょう。
そういう表情をしていました。
だけどさすがに、ハン師が見せる独特な「はにかむ」ような笑顔、ちょっとかすれた声で分かりやすい単語を駆使した音楽の旋律のような英語と比べると、ちょっと勝てないかなと感じます。
ハン師は、本当に存在そのものが慈愛に満ちていますね。
終盤は、「死は存在しない」ということ。
ここの部分は、従来からのぼくの主張とまったく同じです。
拙著「小児がん外科医」で、がんで死んでいく何人もの子どもの死を描きました。
研修医の頃のぼくは、「死」は痛みであり、恐怖であり、暗闇であり、悲しみであると思っていました。
そして医師にとって、「子どもの死」は敗北だと思っていた訳です。
だけどたくさんの子どもの死を見る中で、それは間違ったイメージと知りました。
ぼくは「死後の世界」が存在するとか、「霊魂」が存在すると主張している訳ではありません。
ある一点で、何かがブツッと断絶してしまう「死」は存在しない。
子どもの肉体が見えなくなっても、家族の形は決して崩れない。
死に立ち向かった家族は、子どもの死のあとも、その子を含めて家族としての歩みを続けていくのです。
決して、恐怖でもなければ敗北でもありません。
ぼくは死を迎えた子どもの母親に、「死は存在しません」と言い切ったことがあります。
中央公論新社の「小児がん外科医」は大して売れていませんが、このたび、愛媛県の高校生の道徳の授業のサブテキストに、拙著の一部が採録されました。
「死は存在しない」というタイトルの一章です。
ハン師の思想とぼくの雑感を比べるのもおこがましい話ですが、何十人もの子どもの死を見た経験から得た結論が「死は存在しない」ということです。
素晴らしい番組でした。
世界がなくなればいい ― 2015年04月21日 15時42分57秒
私たちが存在している、場としての世界。
これは本当に存在しているのでしょうか?
あなたは、世界があると認識しています。
しかし、あなたの命が果てた後、世界は存在していると言えますか?
あなたは世界を認識できないし、世界は実存しないかもしれない。
ところが、「私」から見ると、そうではない。
あなたが世を去っても、世界は消えないと「私」は知っている。
日本では毎年100万人以上の生命が誕生し、それ以上の命が消えていく。
だが、「私」には世界は不動である。
つまり、世界とは、個人の所有物と言える。
私が治療をしていたがんの少女に、病気が再発した。
病気はものすごい勢いで進展し、私には、この子の命が果てるのは時間の問題だと悟った。
そこで、そのことを少女の母親に説明した。
彼女は泣き崩れ、「世界がなくなればいい」と言った。
彼女の言う世界とはなんだろうか?
最愛の娘を失えば、自分は生きていても意味がないとも言い、同時に、その少女の兄の育児を考えれば、自分は死んではいけないとも言った。
もし、世界というものが一瞬で消滅すれば、少女のことも、少女の兄のことも、夫のことも、自分のことも何も考える必要がなくなる。
だから世界そのものが消えれば良いと思ったのかもしれない。
だが、それはあり得ない。
そんなことは誰でも知っている。
自分の娘が死に向かっている時に、母親はそんなあり得ないことを口走るだろうか?
いや、それはないだろう。
彼女の言いたかった「世界」とは、少女が包含している「運命」とか「定め」とか「人生」そのものではないだろうか?
自分の娘が死ぬ。
こんな理不尽なことがこの世にあるであろうか?
しかし、娘はそういう人生に巻き込まれている。
そこからは逃げられない。
母親は、娘の人生に絶望し、そんな人生ならば、そんな世界ならば、存在しないほうがいいと考える。
だから、母親が言っている世界とは、人生そのものだ。
しかし、人生は娘に付いてくる。
それだけ人生を忌み嫌い、絶望し、嫌悪しても、人生はあきらめない。
人生はあなたに絶望しないのだ。
死を包含した宿運という名の人生が、その娘にまとわりついてくるならば、ぼくが、座して死を待つ必要はないと考えた。
いや、それどころか「死」なんてものは存在しなくて、残った時間の人生に、何を作ることができるかが、生きる価値と考えた。
ぼくはその子を在宅医療に持ち込み、自宅で痛み止めをつかい、点滴をし、旅行を楽しんでもらった。
彼女たち母子は人生を作ったのである。
こうして人生は完結した。世界はなくならないし、なくす必要もない。
自分で作っていけばいい。
これは本当に存在しているのでしょうか?
あなたは、世界があると認識しています。
しかし、あなたの命が果てた後、世界は存在していると言えますか?
あなたは世界を認識できないし、世界は実存しないかもしれない。
ところが、「私」から見ると、そうではない。
あなたが世を去っても、世界は消えないと「私」は知っている。
日本では毎年100万人以上の生命が誕生し、それ以上の命が消えていく。
だが、「私」には世界は不動である。
つまり、世界とは、個人の所有物と言える。
私が治療をしていたがんの少女に、病気が再発した。
病気はものすごい勢いで進展し、私には、この子の命が果てるのは時間の問題だと悟った。
そこで、そのことを少女の母親に説明した。
彼女は泣き崩れ、「世界がなくなればいい」と言った。
彼女の言う世界とはなんだろうか?
最愛の娘を失えば、自分は生きていても意味がないとも言い、同時に、その少女の兄の育児を考えれば、自分は死んではいけないとも言った。
もし、世界というものが一瞬で消滅すれば、少女のことも、少女の兄のことも、夫のことも、自分のことも何も考える必要がなくなる。
だから世界そのものが消えれば良いと思ったのかもしれない。
だが、それはあり得ない。
そんなことは誰でも知っている。
自分の娘が死に向かっている時に、母親はそんなあり得ないことを口走るだろうか?
いや、それはないだろう。
彼女の言いたかった「世界」とは、少女が包含している「運命」とか「定め」とか「人生」そのものではないだろうか?
自分の娘が死ぬ。
こんな理不尽なことがこの世にあるであろうか?
しかし、娘はそういう人生に巻き込まれている。
そこからは逃げられない。
母親は、娘の人生に絶望し、そんな人生ならば、そんな世界ならば、存在しないほうがいいと考える。
だから、母親が言っている世界とは、人生そのものだ。
しかし、人生は娘に付いてくる。
それだけ人生を忌み嫌い、絶望し、嫌悪しても、人生はあきらめない。
人生はあなたに絶望しないのだ。
死を包含した宿運という名の人生が、その娘にまとわりついてくるならば、ぼくが、座して死を待つ必要はないと考えた。
いや、それどころか「死」なんてものは存在しなくて、残った時間の人生に、何を作ることができるかが、生きる価値と考えた。
ぼくはその子を在宅医療に持ち込み、自宅で痛み止めをつかい、点滴をし、旅行を楽しんでもらった。
彼女たち母子は人生を作ったのである。
こうして人生は完結した。世界はなくならないし、なくす必要もない。
自分で作っていけばいい。


最近のコメント