再訪・Apple Store 銀座 〜 Apple Watch への道 ― 2015年05月05日 13時51分40秒
ぐずぐずしている間に42mmのApple Watch (AW) は、7月出荷になってしまいました。
前回、Apple Store 銀座を訪れた時は、場の雰囲気に圧倒されて、AWの画面がどれくらいキレイなのか、バンドの締め方は容易なのか、、、そんなことをチェックする余裕に欠けていました。
で、今日、再訪した訳です。
まず、42mmと38mm問題は実に悩ましい。
ほとんどの男性は42mmを選ぶでしょう。しかしぼくの手首周りは16cmしかない。38mmでも違和感がないんですね。
かと言って、42mmが不格好かと言うとそうでもない。
問題は視力です。ぼくは遠視と近視と乱視があるので、小さい文字はつらい。すると単純に42mmという選択になるのですが、38mmでもけっこうしっかり見えてしまう。
つまり画面の文字や絵が実にキレイなんです。
AWの画面は美しいとしか言いようがありません。
では、軽い分を考えて38mmか? いや、42mmもそんなに重くないんですね。
Appleのお姉さんが「42mmの方がAWらしい」と言っていましたが、なるほど、確かに頷ける。
38mmはただの時計で、42mmはスマート・ウォッチに見えるという指摘です。そうかもしれない。
そしてバンド。ミラネーゼ・ループはカッコいいし、実用性もある。ループになっているので、手をスポッと入れて、バンドを締める。これは楽。ただ、磁石が強力すぎて、バンド同士がくっつくとなかなか外れない。時計の装着というのは片手でやるので、いったん「こんがらがる」と厄介なんです。
ではレザー・ループはどうか? こちらはループと言っても、輪を解放して一直線になります。ここに不安があった。ループ状の方がそのまま手を突っ込めますからね。
ところが、ベルトの端を磁力で「わっか」にくっつけておけば、ループを保つことが可能なんです。
ちょっと慣れは必要ですが、実はこちらの方が、ミラネーゼ・ループよりも着脱が簡単かもしれません。
写真は42mm、レザー・ループ(色はストーン)です。
どうです? カッコいいでしょ?
ブライト・ブルーも実によかった。カジュアルでも学会発表でもいけるかも。
前回、Apple Store 銀座を訪れた時は、場の雰囲気に圧倒されて、AWの画面がどれくらいキレイなのか、バンドの締め方は容易なのか、、、そんなことをチェックする余裕に欠けていました。
で、今日、再訪した訳です。
まず、42mmと38mm問題は実に悩ましい。
ほとんどの男性は42mmを選ぶでしょう。しかしぼくの手首周りは16cmしかない。38mmでも違和感がないんですね。
かと言って、42mmが不格好かと言うとそうでもない。
問題は視力です。ぼくは遠視と近視と乱視があるので、小さい文字はつらい。すると単純に42mmという選択になるのですが、38mmでもけっこうしっかり見えてしまう。
つまり画面の文字や絵が実にキレイなんです。
AWの画面は美しいとしか言いようがありません。
では、軽い分を考えて38mmか? いや、42mmもそんなに重くないんですね。
Appleのお姉さんが「42mmの方がAWらしい」と言っていましたが、なるほど、確かに頷ける。
38mmはただの時計で、42mmはスマート・ウォッチに見えるという指摘です。そうかもしれない。
そしてバンド。ミラネーゼ・ループはカッコいいし、実用性もある。ループになっているので、手をスポッと入れて、バンドを締める。これは楽。ただ、磁石が強力すぎて、バンド同士がくっつくとなかなか外れない。時計の装着というのは片手でやるので、いったん「こんがらがる」と厄介なんです。
ではレザー・ループはどうか? こちらはループと言っても、輪を解放して一直線になります。ここに不安があった。ループ状の方がそのまま手を突っ込めますからね。
ところが、ベルトの端を磁力で「わっか」にくっつけておけば、ループを保つことが可能なんです。
ちょっと慣れは必要ですが、実はこちらの方が、ミラネーゼ・ループよりも着脱が簡単かもしれません。
写真は42mm、レザー・ループ(色はストーン)です。
どうです? カッコいいでしょ?
ブライト・ブルーも実によかった。カジュアルでも学会発表でもいけるかも。
「子宮頸がんワクチン事件」斎藤 貴男 ― 2015年05月08日 21時58分13秒

製薬会社は資本の論理で動いているので、お金を儲けようと考えるのは当然です。
政治家や役人に働きかけて承認を早めようと考えるのは、自然です。
そして、ワクチンに問題があって、一人でも重い副反応・障害が出れば、ワクチンは中止になるので、製薬会社だって100%安全なワクチンを供給したい訳です。
このワクチンの(いわゆる)被害者の数は多すぎて、今後、ワクチンが再開されることはないでしょう。
普通に考えれば、ワクチンのせいで、こうした障害・病気が発生しているということになりますが、本当の因果関係を確かめるためには、前向きコホート研究が必要です。
しかしそんな研究は絶対におこなわれないでしょう。
サーバリックスもガーダシルも全世界でおこなわれているのですから、副反応の情報収集が甘かったと、製薬会社は非難されてもしかたないと思います。
政治家や役人に働きかけて承認を早めようと考えるのは、自然です。
そして、ワクチンに問題があって、一人でも重い副反応・障害が出れば、ワクチンは中止になるので、製薬会社だって100%安全なワクチンを供給したい訳です。
このワクチンの(いわゆる)被害者の数は多すぎて、今後、ワクチンが再開されることはないでしょう。
普通に考えれば、ワクチンのせいで、こうした障害・病気が発生しているということになりますが、本当の因果関係を確かめるためには、前向きコホート研究が必要です。
しかしそんな研究は絶対におこなわれないでしょう。
サーバリックスもガーダシルも全世界でおこなわれているのですから、副反応の情報収集が甘かったと、製薬会社は非難されてもしかたないと思います。
「聖路加病院訪問看護科―11人のナースたち」 (新潮新書) 上原 善広 ― 2015年05月09日 21時55分13秒

訪問看護師は今後ますます増えていくことでしょう。
時代が要請していますので。
時代が要請していますので。
「役者は一日にしてならず」春日 太一 ― 2015年05月11日 22時50分43秒
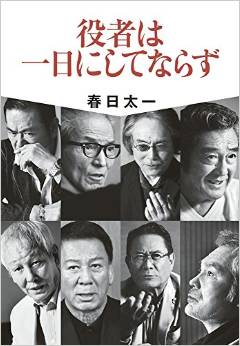
これは傑作だと思います。
一読すると、ベテラン俳優さんの「独白」のように感じられます。
だけど実際はそうでないはず。
著者の巧みな質問によって、俳優さんが言葉を深く深く紡いでいったのだと思います。
で、本書では地の文はほんのわずか、必要最小限。
ですから相当な、取捨選択・編集・校正作業があったと推測します。
これほど深みのあるインタビュー集は、ちょっとお目にかかれないでしょうね。
一読すると、ベテラン俳優さんの「独白」のように感じられます。
だけど実際はそうでないはず。
著者の巧みな質問によって、俳優さんが言葉を深く深く紡いでいったのだと思います。
で、本書では地の文はほんのわずか、必要最小限。
ですから相当な、取捨選択・編集・校正作業があったと推測します。
これほど深みのあるインタビュー集は、ちょっとお目にかかれないでしょうね。
「ゴーストライター論」 (平凡社新書) 神山 典士 ― 2015年05月13日 17時47分33秒

「ゴーストライター」というよりも、「チーム・ライティング」と表現した方がいいという提言です。
なるほど、とても納得できました。
本は作ることも、売ることも大変難しいことです。
チーム・ライティングの人たちはものすごい努力をしていると思います。
また、最近の本は、プロの作家が書いていても、編集部主導で本を作るとも聞きました。
(NHKラジオ・著者に聞きたい本のツボ)
プロの作家さんも、そのチームの一員になる訳ですね。
作家さんだけの力では、なかなかベストセラーは生まれないかもしれません。
なるほど、とても納得できました。
本は作ることも、売ることも大変難しいことです。
チーム・ライティングの人たちはものすごい努力をしていると思います。
また、最近の本は、プロの作家が書いていても、編集部主導で本を作るとも聞きました。
(NHKラジオ・著者に聞きたい本のツボ)
プロの作家さんも、そのチームの一員になる訳ですね。
作家さんだけの力では、なかなかベストセラーは生まれないかもしれません。
「神さまに質問―筋ジストロフィーを生きたぼくの19年」栗原 征史 ― 2015年05月16日 16時13分44秒
筋ジストロフィーの患者さんの闘病記は複数ありますので、本書もそうしたものの一つであろうと、(表現は適切でないかもしれませんが)軽い気持ちで読み始めました。
ところが大変衝撃的な内容でした。
まず、12歳の子ども手記ということ自体が希有なものです。
歩けなくなっていく自分をどう思い、どう表現していくか、こんな記録はそうそう見ることができません。
そしてイジメ。
胸が痛くなります。
栗原君をイジメたクラスメートは、現在では激しく後悔しているでしょう。
ですが、親は一体どういう教育をしていたのかと、ぼくは大きな声を上げたくなります。
さらには、国立Z病院に入院し(母が手術を受けるため、栗原君は一時預かり。そういうシステムが当時は無く、ICUに入る)、人工呼吸器を装着した筋ジストロフィーの患者さんを見ることになる。
栗原君は、自分が20歳までしか生きられないと知ります。
そして同じ病気の友人が19歳で相次いで亡くなります。
ぼくは「知識」として筋ジストロフィーを理解していましたが、10代の青春期にある若者が、どれほどの恐怖感を味わうのか骨身に沁みて理解できました。
人は生まれた瞬間に死ぬことが決まっている。
だから生まれたことの意味を作っていく。
そうしたことを彼は表現していました。
さまざまな病気の闘病記や、障害者に関する本をこれまで多々読んできましたが、本書は長く記憶に留まる名著です。
なお、栗原さんのHPは、以下のURL。
http://www.geocities.jp/kseiji94/index.html?
ところが大変衝撃的な内容でした。
まず、12歳の子ども手記ということ自体が希有なものです。
歩けなくなっていく自分をどう思い、どう表現していくか、こんな記録はそうそう見ることができません。
そしてイジメ。
胸が痛くなります。
栗原君をイジメたクラスメートは、現在では激しく後悔しているでしょう。
ですが、親は一体どういう教育をしていたのかと、ぼくは大きな声を上げたくなります。
さらには、国立Z病院に入院し(母が手術を受けるため、栗原君は一時預かり。そういうシステムが当時は無く、ICUに入る)、人工呼吸器を装着した筋ジストロフィーの患者さんを見ることになる。
栗原君は、自分が20歳までしか生きられないと知ります。
そして同じ病気の友人が19歳で相次いで亡くなります。
ぼくは「知識」として筋ジストロフィーを理解していましたが、10代の青春期にある若者が、どれほどの恐怖感を味わうのか骨身に沁みて理解できました。
人は生まれた瞬間に死ぬことが決まっている。
だから生まれたことの意味を作っていく。
そうしたことを彼は表現していました。
さまざまな病気の闘病記や、障害者に関する本をこれまで多々読んできましたが、本書は長く記憶に留まる名著です。
なお、栗原さんのHPは、以下のURL。
http://www.geocities.jp/kseiji94/index.html?
「命の詩に心のVサイン―筋ジストロフィーを生きたぼくの26年」栗原 征史 ― 2015年05月17日 22時22分27秒
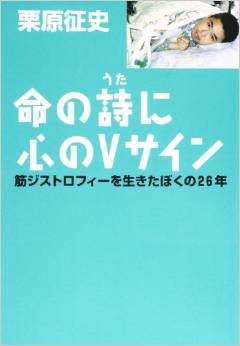
続けて読みました。
人工呼吸器を装着することに対する不安。
性の悩み。
介護疲れで母子心中したくなる心理。
神さまに質問したくなる気持ちがとてもよくわかります。
人工呼吸器を装着することに対する不安。
性の悩み。
介護疲れで母子心中したくなる心理。
神さまに質問したくなる気持ちがとてもよくわかります。
「卵子探しています: 世界の不妊・生殖医療現場を訪ねて」 宮下 洋一 ― 2015年05月19日 19時31分32秒

今週号の週刊現代に、宮下洋一さんの「卵子探しています」の書評を書かせて頂きました。
「週刊現代」も「卵子探しています」もぜひ読んでみてください。
「週刊現代」も「卵子探しています」もぜひ読んでみてください。
「敗北を抱きしめて 増補版―第二次大戦後の日本人」John W. Dower ― 2015年05月23日 23時17分35秒

増補版が出ているとは知りませんでした。
なぜ日本が「世界征服」を企み、誰も止められず、挙げ句破滅し、貧困のどん底から立ち上がることができたのか、本当に不思議です。
この本には大事なことがたくさん書かれています。
日本人が軍国主義・超国家主義の台頭を許した理由は、「人間性・人格・個性」を十分に尊重しなかったからだという指摘があります。
このことは、現在の日本にも言える欠点だとぼくは考えます。
「人間性」とは、人が人として尊重されることです。
「人格」とは、人間を独立した個体として承認することです。
「個性」とは、私たちの中にある多様性を大事にすることです。
こうしたことが蔑ろにされた時、沖縄の基地問題・ヘイトスピーチ・障害者差別やマイノリティー差別が露わになるのだと思います。
日本は「上からの民主主義」を(占領軍から)与えられ、日本国憲法は世界で最も進歩的な内容になり、多くの面でアメリカ民主主義を凌駕しました(実は1945年頃、アメリカは帝国主義国家だった)。
現在、その民主主義が後退しようとしているのは大変残念ですが、まだ憲法は死んでいません。
これをどう生かすかは、やはり日本人の精神性によると考えます。
「人間性・人格・個性」を尊重できるかどうかが鍵になるのではないでしょうか?
なぜ日本が「世界征服」を企み、誰も止められず、挙げ句破滅し、貧困のどん底から立ち上がることができたのか、本当に不思議です。
この本には大事なことがたくさん書かれています。
日本人が軍国主義・超国家主義の台頭を許した理由は、「人間性・人格・個性」を十分に尊重しなかったからだという指摘があります。
このことは、現在の日本にも言える欠点だとぼくは考えます。
「人間性」とは、人が人として尊重されることです。
「人格」とは、人間を独立した個体として承認することです。
「個性」とは、私たちの中にある多様性を大事にすることです。
こうしたことが蔑ろにされた時、沖縄の基地問題・ヘイトスピーチ・障害者差別やマイノリティー差別が露わになるのだと思います。
日本は「上からの民主主義」を(占領軍から)与えられ、日本国憲法は世界で最も進歩的な内容になり、多くの面でアメリカ民主主義を凌駕しました(実は1945年頃、アメリカは帝国主義国家だった)。
現在、その民主主義が後退しようとしているのは大変残念ですが、まだ憲法は死んでいません。
これをどう生かすかは、やはり日本人の精神性によると考えます。
「人間性・人格・個性」を尊重できるかどうかが鍵になるのではないでしょうか?
特別支援学校探訪記 ― 2015年05月27日 16時46分27秒

特別支援学校を見学してきました。
ここには、およそ100名の生徒が通学してきます。
支援の対象は「肢体不自由」です。したがってほとんどの生徒が車椅子を使用しています。
歩けないという不自由のみの子もいますが、心身障害も伴っていて、会話ができない生徒も数多くいます。
気管切開した子も珍しくありませんし、少数ながら人工呼吸器を付けた子もいます。
生徒の数に匹敵するくらい多くの教師がいます。また看護師もいます。
ぼくが見学したクラスは、中学1年。生徒は4人。先生は3人でした。
1時間目は、体を動かす時間。
登校してくる時刻にはかなりばらつきあるため、まだみんな揃いません。
2時間目は学年集会。
寄宿舎の談話室に集まります。生徒は8人。先生は7人。
「気球に乗ってどこまでも」
「怪獣のバラード」が、CDラジカセから流れてきます。
生徒たちは、「あーあーあー」とか「うーうーうー」とか騒いでいる子もいるし、視点を固定してあまり表情の無い子もいます。
騒々しいとか、暗いという印象はまるでなく、賑やかで明るいなと思えました。
歌が終わると、「ボッチャ」です。
直径10メートルくらいの大きな布が4色に区切られています。
それぞれの色に点数を決めて、生徒が順番にボールを投げます。
ボールが止まった色が、その生徒の得点です。
ボールを投げることができない子には、雨どいを用意します。
ボールを離すと、先生が支える雨どいをボールが転がっていきます。
さて、授業は3時間目に。
ぼくはその間、校長先生にインタビューをさせて頂きます。
校長先生の想いは、大変深いものでここではすべてを書くことはできません。
一番重要なメッセージは「自発性」よりも「主体性」が大事ということ。
「自発」とは外部の刺激に反応しているだけの場合があるけれど、「主体」があれば「何かのために」という目的が生まれるので、夢や目標につながるというものでした。
さて、給食の時間。
食堂はかなり広いのですが、生徒がそれ以上に多いし、車椅子の子どもが多いため大変混雑した印象を受けます。
ぼくも頂きました、給食。はい、残さず完食しましたよ。
午後の授業は、中学1年生と3年生で、合同の音楽。
歌を歌い、「聖者が町にやってくる」に併せて全員で合奏です。
実に賑やか。
こうして14時30分に授業終了。
お医者さんの中には、障害が重い子どもを見ると簡単に諦めてしまったり、無駄な治療だと言ったりする人がいます。
いったい何様のつもりでしょうか?
支援学校の先生たちは、どんなに重度の生徒でも分け隔て無く、懸命に心を通わせようと努めていました。
得難い経験をした充実した一日でした。
ここには、およそ100名の生徒が通学してきます。
支援の対象は「肢体不自由」です。したがってほとんどの生徒が車椅子を使用しています。
歩けないという不自由のみの子もいますが、心身障害も伴っていて、会話ができない生徒も数多くいます。
気管切開した子も珍しくありませんし、少数ながら人工呼吸器を付けた子もいます。
生徒の数に匹敵するくらい多くの教師がいます。また看護師もいます。
ぼくが見学したクラスは、中学1年。生徒は4人。先生は3人でした。
1時間目は、体を動かす時間。
登校してくる時刻にはかなりばらつきあるため、まだみんな揃いません。
2時間目は学年集会。
寄宿舎の談話室に集まります。生徒は8人。先生は7人。
「気球に乗ってどこまでも」
「怪獣のバラード」が、CDラジカセから流れてきます。
生徒たちは、「あーあーあー」とか「うーうーうー」とか騒いでいる子もいるし、視点を固定してあまり表情の無い子もいます。
騒々しいとか、暗いという印象はまるでなく、賑やかで明るいなと思えました。
歌が終わると、「ボッチャ」です。
直径10メートルくらいの大きな布が4色に区切られています。
それぞれの色に点数を決めて、生徒が順番にボールを投げます。
ボールが止まった色が、その生徒の得点です。
ボールを投げることができない子には、雨どいを用意します。
ボールを離すと、先生が支える雨どいをボールが転がっていきます。
さて、授業は3時間目に。
ぼくはその間、校長先生にインタビューをさせて頂きます。
校長先生の想いは、大変深いものでここではすべてを書くことはできません。
一番重要なメッセージは「自発性」よりも「主体性」が大事ということ。
「自発」とは外部の刺激に反応しているだけの場合があるけれど、「主体」があれば「何かのために」という目的が生まれるので、夢や目標につながるというものでした。
さて、給食の時間。
食堂はかなり広いのですが、生徒がそれ以上に多いし、車椅子の子どもが多いため大変混雑した印象を受けます。
ぼくも頂きました、給食。はい、残さず完食しましたよ。
午後の授業は、中学1年生と3年生で、合同の音楽。
歌を歌い、「聖者が町にやってくる」に併せて全員で合奏です。
実に賑やか。
こうして14時30分に授業終了。
お医者さんの中には、障害が重い子どもを見ると簡単に諦めてしまったり、無駄な治療だと言ったりする人がいます。
いったい何様のつもりでしょうか?
支援学校の先生たちは、どんなに重度の生徒でも分け隔て無く、懸命に心を通わせようと努めていました。
得難い経験をした充実した一日でした。

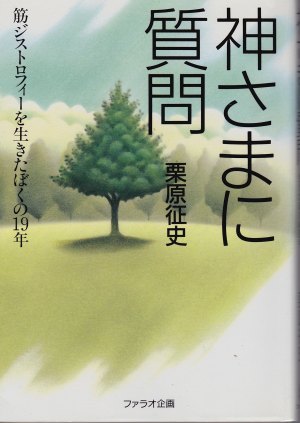
最近のコメント