茶の世界史―緑茶の文化と紅茶の社会 (中公新書) ― 2013年06月22日 21時57分52秒
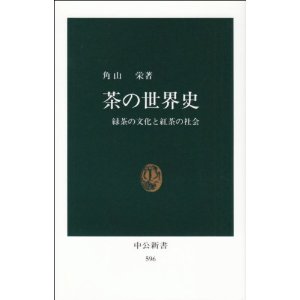
今日は「茶の歴史」を読みました。
面白いことがたくさん書かれていました。
ワールドワイドに世界の文明を見ると、4大文明のうち、中国・インド・オスマン(チグリス・ユーフラテス)は近代まで高いレベルの文化を維持していました。
そのうち中国とインドはイギリスによって滅ぼされたということがよく分かります。
中国はアヘンによって。
インドは、産業革命による綿織物産業の崩壊によって。
しかし考えてみれば、イギリスの嗜好品は何と言っても紅茶であり、原料の茶葉と砂糖はイギリスの植民地から調達されていたというのは、この国の本性を象徴しているような気がします。
ただ、嗜好品といっても、イギリスでは紅茶やチョコレートは貴族階級から広まって最後は大衆のものになります。
紅茶やチョコレートのない時代の労働者は、エネルギーを原料として朝からアルコールを飲んでいたといいますから、イギリスの労働力を根本で支えていたのは砂糖とチョコかもしれません。
その砂糖とチョコはアフリカから拉致されてきた人たちによって作られていた訳です。
そんなに昔の話ではないですよ。拉致のうえに、奴隷です。
むごいですね。
さて、本書には「二グロ奴隷」という単語が出てきますが、いくら何でも時代とずれているのではないでしょうか?
34版ですから、注釈くらい入っていてもいいような気がします。
面白いことがたくさん書かれていました。
ワールドワイドに世界の文明を見ると、4大文明のうち、中国・インド・オスマン(チグリス・ユーフラテス)は近代まで高いレベルの文化を維持していました。
そのうち中国とインドはイギリスによって滅ぼされたということがよく分かります。
中国はアヘンによって。
インドは、産業革命による綿織物産業の崩壊によって。
しかし考えてみれば、イギリスの嗜好品は何と言っても紅茶であり、原料の茶葉と砂糖はイギリスの植民地から調達されていたというのは、この国の本性を象徴しているような気がします。
ただ、嗜好品といっても、イギリスでは紅茶やチョコレートは貴族階級から広まって最後は大衆のものになります。
紅茶やチョコレートのない時代の労働者は、エネルギーを原料として朝からアルコールを飲んでいたといいますから、イギリスの労働力を根本で支えていたのは砂糖とチョコかもしれません。
その砂糖とチョコはアフリカから拉致されてきた人たちによって作られていた訳です。
そんなに昔の話ではないですよ。拉致のうえに、奴隷です。
むごいですね。
さて、本書には「二グロ奴隷」という単語が出てきますが、いくら何でも時代とずれているのではないでしょうか?
34版ですから、注釈くらい入っていてもいいような気がします。



最近のコメント