金閣寺 (新潮文庫) 三島 由紀夫 ― 2013年09月01日 20時39分59秒
文学が到達しうる頂上のうちの一つかなと思います。
金閣寺放火事件をモチーフにしていることは誰もが読む前に知っていますから、その動機を三島に説明して欲しいと読者は思うわけです。
ですが、説明はありません。
あるのは、金閣寺の美しさの描写と、吃りの青年の心象風景の描写だけです。
一行一行、いえ、一文字ずつに重量があり、深く、濃い。
だけど読む方は疲れるかというと、そうではない。
吃りの青年の心の中に引きづり込まれていくので、読み手のスピードが落ちることはありません。
主人公の青年は「現実」を掴むことができない。なぜならば吃りだから。
言葉を口にした時は、すでに現実は移ろっている。
そのずれを彼は憎んでいる。
青年が女を抱こうとすると、必ず金閣寺が現れて、その美を見せつけることで、現実を遮断してしまう。
彼が美しいと想っていた女性は本の出だしで死んでしまっていて、その後に現れる女性はすべて「美」とは言えない実在なんですね。
だから、女性に触れることができないというのは、吃ることと同じ、つまり世界に自分が参加できない。
金閣寺は青年を「美」で圧倒し、世界から放逐してしまうんですね。
世界を変えるのは、「認識」なのか「行為」なのか?
友人が「認識」であると考えるのに対して、主人公の吃りの青年は「行為」と断じます。
そして、人間を「モータル」(死ぬ運命にあるという意)と定義し、金閣寺を永遠の美と捉える。
だから、モータルの人間を殺しても意味がない。
一方で、金閣寺を焼き払ってしまえば、人間は己が築きあげた、そして未来永劫に継続するはずの「美」(死の運命から逃れている)を失ってしまう。
だからこそ、吃りの青年は金閣寺に火を放つのです。
放火の場面で、青年は菓子パンと最中を喰います。
ここの場面が最高にリアルでした。
結末が定まっている物語を、「狂気」ではないもの、すなわち、世界に対する認識で描いてみせる、ほとんど完璧と言っていい作品です。
金閣寺放火事件をモチーフにしていることは誰もが読む前に知っていますから、その動機を三島に説明して欲しいと読者は思うわけです。
ですが、説明はありません。
あるのは、金閣寺の美しさの描写と、吃りの青年の心象風景の描写だけです。
一行一行、いえ、一文字ずつに重量があり、深く、濃い。
だけど読む方は疲れるかというと、そうではない。
吃りの青年の心の中に引きづり込まれていくので、読み手のスピードが落ちることはありません。
主人公の青年は「現実」を掴むことができない。なぜならば吃りだから。
言葉を口にした時は、すでに現実は移ろっている。
そのずれを彼は憎んでいる。
青年が女を抱こうとすると、必ず金閣寺が現れて、その美を見せつけることで、現実を遮断してしまう。
彼が美しいと想っていた女性は本の出だしで死んでしまっていて、その後に現れる女性はすべて「美」とは言えない実在なんですね。
だから、女性に触れることができないというのは、吃ることと同じ、つまり世界に自分が参加できない。
金閣寺は青年を「美」で圧倒し、世界から放逐してしまうんですね。
世界を変えるのは、「認識」なのか「行為」なのか?
友人が「認識」であると考えるのに対して、主人公の吃りの青年は「行為」と断じます。
そして、人間を「モータル」(死ぬ運命にあるという意)と定義し、金閣寺を永遠の美と捉える。
だから、モータルの人間を殺しても意味がない。
一方で、金閣寺を焼き払ってしまえば、人間は己が築きあげた、そして未来永劫に継続するはずの「美」(死の運命から逃れている)を失ってしまう。
だからこそ、吃りの青年は金閣寺に火を放つのです。
放火の場面で、青年は菓子パンと最中を喰います。
ここの場面が最高にリアルでした。
結末が定まっている物語を、「狂気」ではないもの、すなわち、世界に対する認識で描いてみせる、ほとんど完璧と言っていい作品です。
中村勝雄さんにお会いする ― 2013年09月02日 23時46分49秒
30日の贈賞式で、中村勝雄さんにお会いしました。
お祝いの言葉を言いに来て下さり、大変嬉しく思いました。
昨日と今日で中村さんの本を2冊読みました。
「パラダイスウォーカー 車椅子で挑んだハワイ・香港ひとり旅」
「もう一度、抱きしめたい 脳性まひの僕に舞い降りたダウン星の王子さま」
前者は「第8回小学館ノンフィクション大賞優秀賞」を受賞していますので、僕がこれ以上誉める必要はないでしょう。
後者は、それ以上に素晴らしい作品かもしれません。
中村さんと奥さんの結婚の場面や、ダウン症の子を授かってしまった時の動揺と、同時に我が子への深い愛情など、読むべき場面が山ほどあります。
「脳性まひ」という言葉を知らない人はいないと思いますが、「脳性まひ」の作家が書いた本を読んだ経験のある人はあまりいないのではないでしょうか?
ぜひ、多くの人に手に取って欲しいと思います。
お祝いの言葉を言いに来て下さり、大変嬉しく思いました。
昨日と今日で中村さんの本を2冊読みました。
「パラダイスウォーカー 車椅子で挑んだハワイ・香港ひとり旅」
「もう一度、抱きしめたい 脳性まひの僕に舞い降りたダウン星の王子さま」
前者は「第8回小学館ノンフィクション大賞優秀賞」を受賞していますので、僕がこれ以上誉める必要はないでしょう。
後者は、それ以上に素晴らしい作品かもしれません。
中村さんと奥さんの結婚の場面や、ダウン症の子を授かってしまった時の動揺と、同時に我が子への深い愛情など、読むべき場面が山ほどあります。
「脳性まひ」という言葉を知らない人はいないと思いますが、「脳性まひ」の作家が書いた本を読んだ経験のある人はあまりいないのではないでしょうか?
ぜひ、多くの人に手に取って欲しいと思います。
インフルエンザ・ワクチン2013 ― 2013年09月03日 23時19分27秒
昨日からインフルエンザ・ワクチンの予約を取り始めました。
携帯電話・PC(スマートフォン)からのみの予約になります。
http://0432905877.com/i/
今年度から予約枠(接種する患者さんの人数)を少し減らしました。
全部で1000人弱の枠ですが、初日で100人以上の予約が入っています。
どこのクリニックで接種しても、注射の「中身」は同じですから効果は同じですが、うちのクリニックでの接種を希望する方は、早めに予約を入れて下さい。
キャンセルする時も、携帯・PCからどうぞ。
無断キャンセルされると、薬を捨てることになります。
それだけはご容赦ください。
携帯電話・PC(スマートフォン)からのみの予約になります。
http://0432905877.com/i/
今年度から予約枠(接種する患者さんの人数)を少し減らしました。
全部で1000人弱の枠ですが、初日で100人以上の予約が入っています。
どこのクリニックで接種しても、注射の「中身」は同じですから効果は同じですが、うちのクリニックでの接種を希望する方は、早めに予約を入れて下さい。
キャンセルする時も、携帯・PCからどうぞ。
無断キャンセルされると、薬を捨てることになります。
それだけはご容赦ください。
老眼に苦しむ ― 2013年09月04日 22時52分29秒
老人の繰り言になりますが、最近また老眼が悪化しました。
クリニックに2つ、自宅に4つ老眼鏡を持っていますが、どれも合わない。
5つは弱すぎるし、1つは端の方が歪んでしまう。
みなさん、どうしているのでしょうか?
現在読んでいる本は、新潮文庫のかなり昔に作られた本なので、活字が非常に小さい。
だからどうやっても読みがたい。
なので、なかなか進みません。
しかたないので、同じ本の単行本を中古で注文しました。
まだ届いていませんが、文字が大きいと良いのですが。
高校生の頃から20代までは「速読」ができましたが、あれは目が良かったからでしょう。
今は必死になって一文字ずつ読んでいるといった感じ。
こんなザマでは生涯にあとどれだけ本が読めるのか不安です。
愚痴になってしまいました。
こんな駄文に付き合って頂き恐縮です。
クリニックに2つ、自宅に4つ老眼鏡を持っていますが、どれも合わない。
5つは弱すぎるし、1つは端の方が歪んでしまう。
みなさん、どうしているのでしょうか?
現在読んでいる本は、新潮文庫のかなり昔に作られた本なので、活字が非常に小さい。
だからどうやっても読みがたい。
なので、なかなか進みません。
しかたないので、同じ本の単行本を中古で注文しました。
まだ届いていませんが、文字が大きいと良いのですが。
高校生の頃から20代までは「速読」ができましたが、あれは目が良かったからでしょう。
今は必死になって一文字ずつ読んでいるといった感じ。
こんなザマでは生涯にあとどれだけ本が読めるのか不安です。
愚痴になってしまいました。
こんな駄文に付き合って頂き恐縮です。
個人的な体験 (新潮文庫) 大江 健三郎 ― 2013年09月08日 21時05分55秒
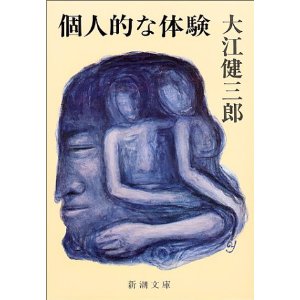
「個人的な体験」というタイトルですが、決して「私小説」ではありません。
もちろんお子さんの病気(障害)をモチーフにしていますが、ここに書かれていることはほぼすべてが創造でしょう。
主人公は鳥(バード)。
鳥(バード)というのは翼を持ち自由に空を飛ぶ生き物です。
ところがこの鳥(バード)は大変不自由な上、まるで老人のような弱々しい存在です。
自分のお嫁さんが赤ちゃんを出産しようとしているのに、アフリカ旅行を夢見る現実回避の男です。
そのアフリカ旅行もロードマップを買うだけで、何の準備もできていないと言っていいかと思います。
職業は、予備校の講師。
こういう言い方は大変失礼かもしれませんが、銀行員などとは違ってとても危ういポジションにいます。
そんな鳥(バード)が授かった赤ちゃんには頭瘤という病気(将来に障害を残す)があります。
彼は自分の子どもを「怪物」と表現します。
つまり完全に我が子を拒んでいるのですね。
そしてその拒絶感は、鳥(バード)の義母も同様です。
彼と義母は、赤ちゃんが命果てることを望み、そのように仕向けます。
赤ちゃんは取り上げた産科医もそれは同じです。
生命の誕生にあたって、産科医は赤ちゃんの男女の別を真っ先に両親に伝えるものです。
ところがこの医者は「忘れちゃったなあ」とまるで他人事です。
未来に向かって生きていく「人」として見なしていないのですね。
そしてはっきりと「早く死ぬほうがいいだろう」と言います。
この本が書かれた時代を考えると、ある意味リアルだとも言えます。
赤ちゃんは鳥(バード)からどんどん遠ざかり、彼の手には触れないところへ行ってしまいます。
抱かなければ何の愛情も生まれません。
親族にとって頭瘤という奇形は、拒否したい病気であって、義母は赤ちゃんの病気を心臓病にしようとします。
ここにはっきりと障害児に対する偏見が表出されています。
この赤ちゃんは心臓病で死ぬのです。
鳥(バード)は人生を正面から受け止めようとしません。
だから障害児を授かったこと「罰」と受け止めます。これでは「受容」は不可能です。
結果、鳥(バード)は酒と性欲に逃走をはかり、自分の赤ちゃんを「生涯の最初で最大の敵」と考えるに至ります。
だから赤ちゃんの入院手続きのために3万円払う際に、アフリカへ旅する標識を抜き取られるような感覚に陥ります。
悲惨ですね。
だけどちょっと示唆に富むことも鳥(バード)は言っているんです。
個人的な体験の洞穴をどんどん進んでいくと、やがて、人間一般にかかわる真実の展望のひらける抜け道に出ることができると(意訳です)。
でも鳥(バード)は全然、そいうことを実行できず、ひたすら絶望的に深く掘り進んで行ってしまう。
なかなか死なない赤ちゃんを見て、鳥(バード)は我が子を「殺人医」のもとへ連れて行きます。
ここでも彼は無責任なんです。つまり、他人によって赤ちゃんを殺してもらおうと考えているから。
そこで命の究極において彼は悟ります。
「欺瞞なしの方法は、自分の手で直接に縊り殺すか、あるいは、かれをひきうけて育ててゆくかの、ふたつにひとつしかない」と。
鳥(バード)が我が子を受容するのは、最後の7ページの段階です。それも突然に何のきっかけもなく受容します。
これは何を意味しているのでしょうか?
小説の中の時間軸では数日に過ぎませんが、本という体裁の中では、2%のページ数しか我が子を受容していません。
つまり自分の子どもの障害を受容するためには時間がかかるということを暗示しており、受容には明確なきっかけがないことを意味しているのです。
そしてさらに重要なことは、最後の7ページで、鳥(バード)の義父母は完全に障害児を受容しています。
あれ程、障害児の死を望んだ義母がなぜこんなに簡単に受容してしまったのでしょうか?
それは、これが本当の受容ではないからです。
「仮りの受容」と言ってもいいし、「螺旋型の受容」と言ってもいい。
つまり鳥(バード)の家族はどこかの時点で、この赤ちゃんを再度、拒否する可能性があること暗示している訳です。
障害の受容とは何かということを描ききった大江健三郎先生の初期の大傑作です。
だけど、障害児と関わった経験の無い読者にはちょっと難しい本かもしれません。
もちろんお子さんの病気(障害)をモチーフにしていますが、ここに書かれていることはほぼすべてが創造でしょう。
主人公は鳥(バード)。
鳥(バード)というのは翼を持ち自由に空を飛ぶ生き物です。
ところがこの鳥(バード)は大変不自由な上、まるで老人のような弱々しい存在です。
自分のお嫁さんが赤ちゃんを出産しようとしているのに、アフリカ旅行を夢見る現実回避の男です。
そのアフリカ旅行もロードマップを買うだけで、何の準備もできていないと言っていいかと思います。
職業は、予備校の講師。
こういう言い方は大変失礼かもしれませんが、銀行員などとは違ってとても危ういポジションにいます。
そんな鳥(バード)が授かった赤ちゃんには頭瘤という病気(将来に障害を残す)があります。
彼は自分の子どもを「怪物」と表現します。
つまり完全に我が子を拒んでいるのですね。
そしてその拒絶感は、鳥(バード)の義母も同様です。
彼と義母は、赤ちゃんが命果てることを望み、そのように仕向けます。
赤ちゃんは取り上げた産科医もそれは同じです。
生命の誕生にあたって、産科医は赤ちゃんの男女の別を真っ先に両親に伝えるものです。
ところがこの医者は「忘れちゃったなあ」とまるで他人事です。
未来に向かって生きていく「人」として見なしていないのですね。
そしてはっきりと「早く死ぬほうがいいだろう」と言います。
この本が書かれた時代を考えると、ある意味リアルだとも言えます。
赤ちゃんは鳥(バード)からどんどん遠ざかり、彼の手には触れないところへ行ってしまいます。
抱かなければ何の愛情も生まれません。
親族にとって頭瘤という奇形は、拒否したい病気であって、義母は赤ちゃんの病気を心臓病にしようとします。
ここにはっきりと障害児に対する偏見が表出されています。
この赤ちゃんは心臓病で死ぬのです。
鳥(バード)は人生を正面から受け止めようとしません。
だから障害児を授かったこと「罰」と受け止めます。これでは「受容」は不可能です。
結果、鳥(バード)は酒と性欲に逃走をはかり、自分の赤ちゃんを「生涯の最初で最大の敵」と考えるに至ります。
だから赤ちゃんの入院手続きのために3万円払う際に、アフリカへ旅する標識を抜き取られるような感覚に陥ります。
悲惨ですね。
だけどちょっと示唆に富むことも鳥(バード)は言っているんです。
個人的な体験の洞穴をどんどん進んでいくと、やがて、人間一般にかかわる真実の展望のひらける抜け道に出ることができると(意訳です)。
でも鳥(バード)は全然、そいうことを実行できず、ひたすら絶望的に深く掘り進んで行ってしまう。
なかなか死なない赤ちゃんを見て、鳥(バード)は我が子を「殺人医」のもとへ連れて行きます。
ここでも彼は無責任なんです。つまり、他人によって赤ちゃんを殺してもらおうと考えているから。
そこで命の究極において彼は悟ります。
「欺瞞なしの方法は、自分の手で直接に縊り殺すか、あるいは、かれをひきうけて育ててゆくかの、ふたつにひとつしかない」と。
鳥(バード)が我が子を受容するのは、最後の7ページの段階です。それも突然に何のきっかけもなく受容します。
これは何を意味しているのでしょうか?
小説の中の時間軸では数日に過ぎませんが、本という体裁の中では、2%のページ数しか我が子を受容していません。
つまり自分の子どもの障害を受容するためには時間がかかるということを暗示しており、受容には明確なきっかけがないことを意味しているのです。
そしてさらに重要なことは、最後の7ページで、鳥(バード)の義父母は完全に障害児を受容しています。
あれ程、障害児の死を望んだ義母がなぜこんなに簡単に受容してしまったのでしょうか?
それは、これが本当の受容ではないからです。
「仮りの受容」と言ってもいいし、「螺旋型の受容」と言ってもいい。
つまり鳥(バード)の家族はどこかの時点で、この赤ちゃんを再度、拒否する可能性があること暗示している訳です。
障害の受容とは何かということを描ききった大江健三郎先生の初期の大傑作です。
だけど、障害児と関わった経験の無い読者にはちょっと難しい本かもしれません。
砂の女 (新潮文庫) 安部 公房 ― 2013年09月11日 21時19分52秒
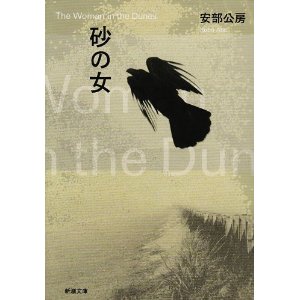
安部公房先生はノーベル文学賞候補にもなった作家で、日本のみならず海外でもファンが多いようです。
現代ではあまり読まれていないかもしれませんが、僕を含めて僕より上の世代の読書好きの人はけっこう読んでいるのではないでしょうか?
その安部公房の代表作が「砂の女」です。
寓話みたいな作品で、この本で描かれているのは主人公の「不条理」でしょう。
しかし寓話は寓話として終了し、不条理を突破するヒントみたいなものはありません。
話としてはものすごく面白くて一気に読んでしまうのですが、不条理の先にあるものを表現しないというのは、文学としてどうなんでしょうか?
ま、僕は純文学に詳しい訳でもなければ一家言ある訳でもないので、面白ければ「良い」という立場ですが、文学の使命とは何かと戸惑ったりします。
労働(この場合は砂を掻き出す)を自己否定と捉え、なおかつ、そのエネルギーを真の労働価値と定義する台詞が、本書の全体を表現しています。
本来であれば、人間は労働によってのみでしか自己実現できない(健常者の話です)訳ですが、この主人公は「労働力の再生産費」すら得られない。搾取されるているどころか、生存のために労働している訳ですね。
ところが最終の場面になると、自己実現を放棄してしまう。
つまりこのままで「良い」となる。
不条理に対する人間の不可思議な反応。
そういうことを安部公房は言いたかったのでしょうか。
現代ではあまり読まれていないかもしれませんが、僕を含めて僕より上の世代の読書好きの人はけっこう読んでいるのではないでしょうか?
その安部公房の代表作が「砂の女」です。
寓話みたいな作品で、この本で描かれているのは主人公の「不条理」でしょう。
しかし寓話は寓話として終了し、不条理を突破するヒントみたいなものはありません。
話としてはものすごく面白くて一気に読んでしまうのですが、不条理の先にあるものを表現しないというのは、文学としてどうなんでしょうか?
ま、僕は純文学に詳しい訳でもなければ一家言ある訳でもないので、面白ければ「良い」という立場ですが、文学の使命とは何かと戸惑ったりします。
労働(この場合は砂を掻き出す)を自己否定と捉え、なおかつ、そのエネルギーを真の労働価値と定義する台詞が、本書の全体を表現しています。
本来であれば、人間は労働によってのみでしか自己実現できない(健常者の話です)訳ですが、この主人公は「労働力の再生産費」すら得られない。搾取されるているどころか、生存のために労働している訳ですね。
ところが最終の場面になると、自己実現を放棄してしまう。
つまりこのままで「良い」となる。
不条理に対する人間の不可思議な反応。
そういうことを安部公房は言いたかったのでしょうか。
今夜の顔は ― 2013年09月16日 21時29分50秒
10月から始まるインフルエンザ・ワクチンの予防接種ですが、10月の枠は2/3くらいはもう埋まっています。
あと2週間で接種が始まりますので、うちのクリニックで接種したい方は、早めの予約してくださいね。
ここから予約できます。
http://0432905877.com/i/
さて、今夜のうちの三女はこんな表情。
あと2週間で接種が始まりますので、うちのクリニックで接種したい方は、早めの予約してくださいね。
ここから予約できます。
http://0432905877.com/i/
さて、今夜のうちの三女はこんな表情。
万延元年のフットボール (講談社文芸文庫) 大江 健三郎 ― 2013年09月18日 23時22分15秒

大江さんの代表作です。
読了するのに1週間くらいかかりましたが、惹きつけられるように、取り憑かれたように、渦に巻き込まれるように、作品世界の中へ入っていきました。
読了するのに1週間くらいかかりましたが、惹きつけられるように、取り憑かれたように、渦に巻き込まれるように、作品世界の中へ入っていきました。
「万延元年のフットボール」をどう読むか ― 2013年09月19日 22時46分03秒
この作品を境にして、大江先生はあちらの方へ行ってしまいました。
あちらというのは、思弁の世界です。
あるいは言語の世界とも言えるし、詩の世界とも言える。
また、文体やリズムとか、音楽を感じさせる世界かもしれない。
「奇妙な仕事」に始まった大江文学は、閉ざされた状況を描くことで、人間の実在を主題にしていました。
ま、分かりやすく言えば、実存主義そのもの。
初期の最高傑作は「死者の奢り」でしょう。
ところが大江先生は私生活において、障害児を授かります。1960年代初期ですから、はっきり言えば、間引かれた命だった可能性も大いにあった。そういう時代です。
おそらく、大江先生は猛烈に葛藤し、最終的に我が子を受け入れ、「個人的な体験」を書いたのでしょう。
ここがひとつの方向転換ですね。
で、同時に作家としてどう生きていくか、何を書いていくか、深く悩んだのではないでしょうか?
障害児を授かるという事実は、哲学的な命題を軽く吹っ飛ばして、実存は本質に先んじようが、どうであろうが、現に障害児が我が子として目の前に存在するという重さに圧倒されてしまったことでしょう。
そして「個人的な体験」の延長に作家人生を見通してしまうと、書きたいことが、文学から離れて、評論とか解説とか説教みたいになってしまうと考えたはずです。
そこでさらにもうひとつ転換して、障害児を授かったことは保留しながら、で、同時にそこから離れて、純粋な文学の持つ言葉の可能性に挑戦したのではないでしょうか。この万延元年のフットボールで。
本作で、主人公は自分たち夫婦の障害児を見捨てているんです。
これを、「個人的な体験」のその後と捉えて、「個人的な体験」で受け入れた子どもを突き放しているので、あれは「仮の受容」だったという解釈もあろうかと思いますが、それはちょっと違うでしょう。
先日も書きましたが、「仮の受容」の暗示は、「個人的な体験」のラスト数ページで書き尽くされているのです。
本作では、そういうことを書きたかったのではない。
主人公は、友人の奇妙な自殺を自分に重ねて、自分の「根」を失い、未来に向かって進めなくなっている。
夫婦の仲も破綻しているし、障害児の将来に展望もない。
だから、この主人公は時間軸で言うと、横にしか動けない。
過去を振り返ることはあっても、評論家のような非・当事者のような態度を取る。コミットしない。
一方、主人公の弟は、100年前に万延元年の一揆を自分に重ねて、過去から現在に至る時間の流れを一身に受け止めている。
弟は親衛隊を組織して(フットボール・チームを作り)、村に暴動を起こす。
だけど誰が考えてもこの暴動に未来は無いんです。
従って、弟が辿る生命のどん詰まりを読者は予言できる。
兄と弟は、時間の流れにおいて「丁字」に衝突することが本作の骨格になっている。
そしてその衝突において、ふたつの破壊、すなわち、主人公の妹の破滅と、主人公の妻の破滅が描かれる。
だけど、小さな希望もあって、それは、夫婦は二人の子どもを育てようと、困難を背負い込むところにそれが現れている。
しかしこの困難はかなり大きなもので、本当に主人公に未来は見えているのか、読者は懸命に考える必要に迫られます。
こういったことを、大江先生は決して平易には書いていません。
だけどそれは「難解」とは違うと思う。
こういう文章・文体・表現は、音楽と同じで、そういった文字を奏でることで四国の森の中の「立体」と、100年に及ぶ「時間」が浮き上がるのではないか。
だから、万延元年のフットボールは、この文章以外では成り立たないと思います。
文学とはこういうものだと思うし、文字に力があるとは、こういう本を指すのでしょう。
ノーベル文学賞を受賞した時に、本作がその受賞理由のひとつになったと聞きます。
それは大変納得できるのですが、ヨーロッパ言語で大江文学が本当に理解できるのかについては大変疑問です。
1967年の作品ですから、現代の人から見ればもう完全に古典でしょう。
しかし元々「時代」や「今」を描いた作品ではないので、若い人にも読んでもらいたいなと思います。
あちらというのは、思弁の世界です。
あるいは言語の世界とも言えるし、詩の世界とも言える。
また、文体やリズムとか、音楽を感じさせる世界かもしれない。
「奇妙な仕事」に始まった大江文学は、閉ざされた状況を描くことで、人間の実在を主題にしていました。
ま、分かりやすく言えば、実存主義そのもの。
初期の最高傑作は「死者の奢り」でしょう。
ところが大江先生は私生活において、障害児を授かります。1960年代初期ですから、はっきり言えば、間引かれた命だった可能性も大いにあった。そういう時代です。
おそらく、大江先生は猛烈に葛藤し、最終的に我が子を受け入れ、「個人的な体験」を書いたのでしょう。
ここがひとつの方向転換ですね。
で、同時に作家としてどう生きていくか、何を書いていくか、深く悩んだのではないでしょうか?
障害児を授かるという事実は、哲学的な命題を軽く吹っ飛ばして、実存は本質に先んじようが、どうであろうが、現に障害児が我が子として目の前に存在するという重さに圧倒されてしまったことでしょう。
そして「個人的な体験」の延長に作家人生を見通してしまうと、書きたいことが、文学から離れて、評論とか解説とか説教みたいになってしまうと考えたはずです。
そこでさらにもうひとつ転換して、障害児を授かったことは保留しながら、で、同時にそこから離れて、純粋な文学の持つ言葉の可能性に挑戦したのではないでしょうか。この万延元年のフットボールで。
本作で、主人公は自分たち夫婦の障害児を見捨てているんです。
これを、「個人的な体験」のその後と捉えて、「個人的な体験」で受け入れた子どもを突き放しているので、あれは「仮の受容」だったという解釈もあろうかと思いますが、それはちょっと違うでしょう。
先日も書きましたが、「仮の受容」の暗示は、「個人的な体験」のラスト数ページで書き尽くされているのです。
本作では、そういうことを書きたかったのではない。
主人公は、友人の奇妙な自殺を自分に重ねて、自分の「根」を失い、未来に向かって進めなくなっている。
夫婦の仲も破綻しているし、障害児の将来に展望もない。
だから、この主人公は時間軸で言うと、横にしか動けない。
過去を振り返ることはあっても、評論家のような非・当事者のような態度を取る。コミットしない。
一方、主人公の弟は、100年前に万延元年の一揆を自分に重ねて、過去から現在に至る時間の流れを一身に受け止めている。
弟は親衛隊を組織して(フットボール・チームを作り)、村に暴動を起こす。
だけど誰が考えてもこの暴動に未来は無いんです。
従って、弟が辿る生命のどん詰まりを読者は予言できる。
兄と弟は、時間の流れにおいて「丁字」に衝突することが本作の骨格になっている。
そしてその衝突において、ふたつの破壊、すなわち、主人公の妹の破滅と、主人公の妻の破滅が描かれる。
だけど、小さな希望もあって、それは、夫婦は二人の子どもを育てようと、困難を背負い込むところにそれが現れている。
しかしこの困難はかなり大きなもので、本当に主人公に未来は見えているのか、読者は懸命に考える必要に迫られます。
こういったことを、大江先生は決して平易には書いていません。
だけどそれは「難解」とは違うと思う。
こういう文章・文体・表現は、音楽と同じで、そういった文字を奏でることで四国の森の中の「立体」と、100年に及ぶ「時間」が浮き上がるのではないか。
だから、万延元年のフットボールは、この文章以外では成り立たないと思います。
文学とはこういうものだと思うし、文字に力があるとは、こういう本を指すのでしょう。
ノーベル文学賞を受賞した時に、本作がその受賞理由のひとつになったと聞きます。
それは大変納得できるのですが、ヨーロッパ言語で大江文学が本当に理解できるのかについては大変疑問です。
1967年の作品ですから、現代の人から見ればもう完全に古典でしょう。
しかし元々「時代」や「今」を描いた作品ではないので、若い人にも読んでもらいたいなと思います。
代替医療解剖 (新潮文庫) サイモン シン, エツァート エルンスト ― 2013年09月23日 20時17分07秒

★★★★★
申し分なく面白かったです。
申し分なく面白かったです。





最近のコメント