女のからだ――フェミニズム以後 (岩波新書) 荻野 美穂 ― 2016年08月21日 18時12分02秒
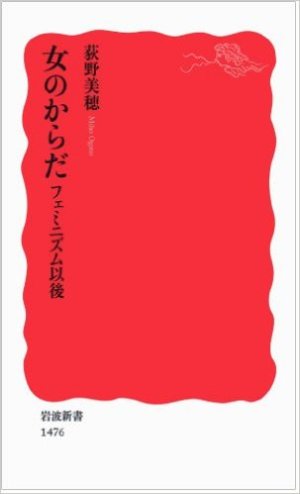
2014年に刊行された新書ですが、勉強のため再読しました。
女性解放運動・フェミニズムは、女性の健康問題ならびに中絶の自由と密接に関連があります。
ただし日本とアメリカを比較すると、中絶に対する女性活動家の考え方には微妙な違いがあります。
それはなぜでしょう?
日本は戦後すぐに中絶が事実上自由化されました。
敗戦によって満州国が崩壊し、大陸からも南方からも凄まじい数の男性兵士が日本に帰還し、日本の人口は爆発的に増えてしまったからです。
人口問題は食糧問題、住宅問題にもなり、人口を制限する必要がでてきました。
従って、国の政策として中絶が自由化されたのです。
ただ、この時の法律は「優生保護法」という名称で、優生学の思想が戦前よりも強く現れていました。
この理由は天皇制が戦前と比較して緩やかになったからです。
戦時中の富国強兵・産めや増やせやの思想の中にあって、あらゆる赤ちゃんは天皇を頂点とした一家の子どもと見なされました。
従って、優生思想はそれほど強くなかったのです。
戦後は、量を絞って、そのぶん質を確保しようとしたわけです。
1950年代に中絶が合法的だった先進国は世界で日本だけでした。
したがって日本は「堕胎天国」という汚名を浴びせられます。
一方アメリカでは、中絶が禁止されていたために女性解放運動・ウイミンズ・リブが立ちあります。
その当時のアメリカ女性は、闇の堕胎師による中絶や、発がん性のあるピルや危険な女性避妊具によって、悲惨な暗闇の道を辿っていたのでした。
それが1972年になって中絶は合法化されます。つまり女性が中絶の権利を勝ち取ったのです。
しかし、猛烈な反発もありました。今もあります。
キリスト教保守派は、受精卵を生命と見なすため、中絶は人殺しという解釈になるのです。
両者の対立は現在も続いており、大統領選の行方さえも決める論争になり続けています。
ですから、女性たちは中絶を「チョイス」することに一切の妥協はしません。
障害胎児を堕ろすことは当然であり、苦しみを持った子を生ませることは道徳的でないという理屈を付けます。
さて、日本は高度成長期に入り、今度は労働人口を必要とするようになりました。このため政府自民党は、中絶の要件から経済的理由を削除し、一方で、胎児条項を設けて障害児を堕胎していいという法改正を行おうとしました。経済的理由が削除されると、中絶は事実上不可能になります。
既得権益を奪われそうになって日本の女性たちも立ち上がりました。中絶の権利を守ろうとしたのです。
ところが反対意見は意外なところから現れました。
脳性マヒ者協会「青い芝」です。
青い芝は、障害胎児を中絶権利があるのかと、女性たちを強く批判しました。
また政府自民党にも強く抗議しました。
政府は、青い芝との論争に敗れ、「胎児条項」を削除しました。
つまり、日本という国は、胎児の障害を理由に堕胎してはいけないのです。このことを私たちはよく知っておかなくてはいけません。
青い芝と女性たちの話し合いは10年以上続きました。
その結果、女性たちの考え方はしだいに変化し、「産む産まないは女(わたし)が決める」から、「産める社会を! 産みたい社会を!」へと変わっていきました。
そして優生思想にははっきりと反対を表明し、中絶の自由とは国家からの自由であり、障害児を堕胎する権利ではないという方向へ向いていきました。
この点が、明らかな日米の違いです。
私の考えとしては、アメリカ保守派のように受精卵にも命があるという中絶禁止思想はちょと極端だと思います。
そして、女性の権利として中絶は自由と言いながら、子を授からないと卵子提供も代理母も何でもOKという姿勢は、生命というものに対して少し大雑把な態度だなと感じます。
女性解放運動・フェミニズムは、女性の健康問題ならびに中絶の自由と密接に関連があります。
ただし日本とアメリカを比較すると、中絶に対する女性活動家の考え方には微妙な違いがあります。
それはなぜでしょう?
日本は戦後すぐに中絶が事実上自由化されました。
敗戦によって満州国が崩壊し、大陸からも南方からも凄まじい数の男性兵士が日本に帰還し、日本の人口は爆発的に増えてしまったからです。
人口問題は食糧問題、住宅問題にもなり、人口を制限する必要がでてきました。
従って、国の政策として中絶が自由化されたのです。
ただ、この時の法律は「優生保護法」という名称で、優生学の思想が戦前よりも強く現れていました。
この理由は天皇制が戦前と比較して緩やかになったからです。
戦時中の富国強兵・産めや増やせやの思想の中にあって、あらゆる赤ちゃんは天皇を頂点とした一家の子どもと見なされました。
従って、優生思想はそれほど強くなかったのです。
戦後は、量を絞って、そのぶん質を確保しようとしたわけです。
1950年代に中絶が合法的だった先進国は世界で日本だけでした。
したがって日本は「堕胎天国」という汚名を浴びせられます。
一方アメリカでは、中絶が禁止されていたために女性解放運動・ウイミンズ・リブが立ちあります。
その当時のアメリカ女性は、闇の堕胎師による中絶や、発がん性のあるピルや危険な女性避妊具によって、悲惨な暗闇の道を辿っていたのでした。
それが1972年になって中絶は合法化されます。つまり女性が中絶の権利を勝ち取ったのです。
しかし、猛烈な反発もありました。今もあります。
キリスト教保守派は、受精卵を生命と見なすため、中絶は人殺しという解釈になるのです。
両者の対立は現在も続いており、大統領選の行方さえも決める論争になり続けています。
ですから、女性たちは中絶を「チョイス」することに一切の妥協はしません。
障害胎児を堕ろすことは当然であり、苦しみを持った子を生ませることは道徳的でないという理屈を付けます。
さて、日本は高度成長期に入り、今度は労働人口を必要とするようになりました。このため政府自民党は、中絶の要件から経済的理由を削除し、一方で、胎児条項を設けて障害児を堕胎していいという法改正を行おうとしました。経済的理由が削除されると、中絶は事実上不可能になります。
既得権益を奪われそうになって日本の女性たちも立ち上がりました。中絶の権利を守ろうとしたのです。
ところが反対意見は意外なところから現れました。
脳性マヒ者協会「青い芝」です。
青い芝は、障害胎児を中絶権利があるのかと、女性たちを強く批判しました。
また政府自民党にも強く抗議しました。
政府は、青い芝との論争に敗れ、「胎児条項」を削除しました。
つまり、日本という国は、胎児の障害を理由に堕胎してはいけないのです。このことを私たちはよく知っておかなくてはいけません。
青い芝と女性たちの話し合いは10年以上続きました。
その結果、女性たちの考え方はしだいに変化し、「産む産まないは女(わたし)が決める」から、「産める社会を! 産みたい社会を!」へと変わっていきました。
そして優生思想にははっきりと反対を表明し、中絶の自由とは国家からの自由であり、障害児を堕胎する権利ではないという方向へ向いていきました。
この点が、明らかな日米の違いです。
私の考えとしては、アメリカ保守派のように受精卵にも命があるという中絶禁止思想はちょと極端だと思います。
そして、女性の権利として中絶は自由と言いながら、子を授からないと卵子提供も代理母も何でもOKという姿勢は、生命というものに対して少し大雑把な態度だなと感じます。



最近のコメント